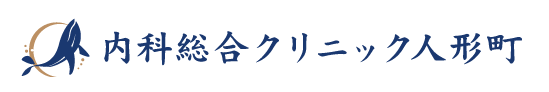院長 藤田
院長 藤田こんばんは。内科総合クリニック人形町 院長の藤田(総合内科専門医)です。
前エントリー(その検査は必要ですか?その2)では診断のプロセスのうち身体所見までについてお話しましたが、
「えっ?熱出てお医者さん行ったらすぐインフルの検査してくれて診断つきましたけど?」
という方も多いかも知れません。実をいうと、この「身体所見を飛ばして検査」というやり方もあながち間違いではありません。なぜなら、「インフルエンザの流行期に急な高熱と節々の痛みで受診された方」のほとんどがインフルエンザだからです。
このことを診断学では「検査前確率が高い」といいます。
このように確率論を使って診断を進めることを「臨床推論」と呼び、今や医師国家試験や専門医試験にも必ず出て来る内科医の必修事項です。
ところで実を言いますと、検査前確率が非常に高い場合、検査の必要はありません。その理由は、ベイズ定理という臨床推論の基礎となる理論を理解しなければ難しいので、興味のある方は下記サイトをご一読下さい。
では、そんなインフルエンザである可能性が高い患者さんでも、あの鼻に綿棒グリグリの検査(正式には「インフルエンザ抗原定性検査」)をやるのは何故なのでしょうか?
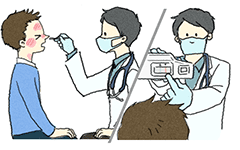
考えられるのは以下のような理由です。
- 病歴・バイタルサイン・身体所見でどこか引っかかるところがある(流行期では無い、症状がやや典型的ではない、など)
- 患者さんが強く検査を希望している、もしくは上司などに検査を受けるよう指示されている。
- 上記のような確率論を説明している時間が無い、もしくは説明しても理解が難しいことが予想される。
①は医学的に妥当な理由です。検査前確率が50%程度と見積もられる場合が、最も検査の有用性が高いのです(これもベイズ定理によります)。
インフルエンザ抗原検査はとても特異度が高い(インフルエンザでは無い場合に陽性となることは殆ど無い)検査なので、結果が陽性ならばインフルエンザとほぼ断定出来ます。
逆に、感度はそんなに高くはありません(検査キットによって60-80%と幅があります)。実際はインフルエンザなのに、検査結果が陰性になることが2-4割もあるのです。よって、検査結果が陰性だった場合でもインフルエンザは否定出来ないのです。
びっくりですよね。インフルエンザかどうか調べるために検査しても結局分からないなんて。でも、それが検査の限界なのです。これは何もインフルエンザ検査に限った事ではなく、感度100%という検査はほとんど存在しません。
例えば、「インフルエンザの流行期に家族がインフルエンザにかかり、その翌日に本人が発熱し体の節々が痛い」という方の場合、検査前確率は90%以上(まあ、まずインフルエンザだろう)と見積もられます。
こういう方にインフルエンザの検査をして、結果が陰性だったとしましょう。検査後確率は多少下がりますが、それでも70%程度です。
検査の結果が陰性だったけれども、「インフルエンザの可能性が70%ある」と言われたら、ほとんどの方が抗インフルエンザ薬の処方を希望されます。時間とお金をかけて痛い検査をしても、結局治療方針は変わらないのです。
「検査前確率が高い場合は検査は必要ない」というのはこういう訳です。このように、検査を行うかどうかの意思決定と結果の解釈を正しく行うには、その検査の特性と限界を知っている必要があります。
しかし、実際の外来でとても多いのが②+③の場合です。

「フジタくん、熱あるの?病院行って検査受けてきなさい。」
みたいなことは、責任感が強く部下思いの上司ほど言いがちなのかもしれません。
ただでさえ高熱で辛い患者さんに小難しい話を長々とし、その結果やはり「上司から言われたので検査してください」と言われ、結果患者さんの心証は悪くなるわ、時間と労力をかけて却って感染拡大してしまうわ、となるくらいなら、最初から患者さんの希望通り検査をするのが総合的に正しい判断と言っていいでしょう。
それに、患者さんを納得・安心させるのも医療の役割という考え方もあります。保険医療に余裕がある限りは、本来は必要性の低い検査を患者さんの納得・安心のために行わざるを得ないことは続くでしょう。
インフルエンザ診療には日本独特の医療を取り巻く事情が凝縮されていると感じているので、今後別途エントリーで書くつもりです。
長くなりましたので、続きは次エントリー(その検査は必要ですか?その4~検査は適切に~)にて。
以上
この記事を書いた人

内科総合クリニック人形町 院長
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医
東京大学医学部保健学科および横浜市立大学医学部を卒業
東京大学付属病院や虎の門病院等を経て2019年11月に当院を開業
最寄駅:東京地下鉄 人形町駅および水天宮前駅(各徒歩3分)