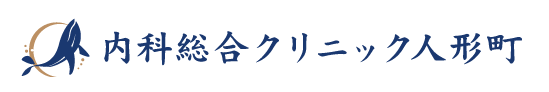みなさん、血圧は右と左、どちらで測っていますか?左右両方で測っているという方はいらっしゃるでしょうか。ほとんどの方は、血圧を測る時の左右の違いを意識していないと思います。
通常、血圧の左右差はなく、左右どちらで測っていただいても問題ありません。ただし、血圧に左右差がでる原因がいくつかあり、治療が必要な場合もあります。
一番重い原因は、大動脈解離という、大動脈が裂けてしまう病気。急激な胸や肩の痛みなどの症状を伴うため、救急車で病院に運ばれるくらいの重篤なものです。また、血管の炎症や動脈硬化で血圧の左右差が出ることも。
今回は、血圧の左右差がなぜ出るのか、どのような原因があるのかについて解説していきます。
この記事の執筆者

藤田 英理 内科総合クリニック人形町 院長
東京大学医学部保健学科、横浜市立大学医学部を卒業。虎の門病院、稲城市立病院、JCHO東京高輪病院への勤務を経て内科総合クリニック人形町を開院。総合内科専門医。AGA治療や生活習慣病指導も行う。
血圧は測り方によってどう変化する?
みなさん、普段どのように血圧を測定していますか?
高血圧で治療中の方は、自宅で家庭用血圧計を使って測定し、記録している方もいらっしゃるでしょう。日本では約4000万台の家庭用血圧計が使われているというデータがあり、これは1世帯に1台の血圧計があるという計算になるそうです1) 。
血圧の測定方法には、家庭用測定器や自動測定器を使って自分で測る方法と、医師や看護師などの医療スタッフが直接聴診器で音を聞きながら血圧を測定する方法が。血圧は、それぞれ使う器械や測定する場所、環境などでも変化してしまいます。
よく知られている例として、定期健診などで白衣をきたスタッフが血圧を測定すると高血圧になってしまい、あとで落ち着いて測り直すと正常ということも。これは、白衣高血圧といって、白衣をきたスタッフに囲まれ病院という特殊な環境に緊張し、起こるとされています。

また、血圧はサーカディアンリズムといって昼〜夜で日内変動をしていますが、夜は昼に比べて10-20%ほど低くなります。
同じ測り方、同じ時間に測っても、1回目、2回目とで血圧が変動することも。これは血圧変動性といい、呼吸の深さや自律神経の働き、また季節ごとによる変化や年々変化が大きくなるなど、多様性があります。
変化すること自体は正常です。例えば、深呼吸で深く息を吸うと血圧は10mmHgほど下がります。血圧が変化すること自体は自律神経の働きによる正常な調節ですが、度を超えて変化したり、変化した血圧が高すぎたりする場合などには、治療が必要です。
左右の腕のどちらで測るかについてですが、普通は左右差はほとんどないか、あっても5mmHg以下。若干の差が見られる原因は、心臓から測定する場所の位置までの距離が違うためです。心臓から見ると、右腕の方が左腕よりも近いため、若干血圧が高くなります。ただし、通常はその距離の差も誤差範囲ですので、血圧自体の差はほとんど生じません。
このように、血圧は多少変動すること自体は正常でも、変動の幅が正常の範囲を超えているかどうか、どのような特徴があるかは非常に重要な指標です。
 院長 藤田
院長 藤田血圧を測る時の一般的な注意点をご紹介しましょう1, 2) 。
- 左右どちらか決まった腕で測る。
- 静かな場所で測る。
- 測定時に会話はしない。
- 腕に直接カフを巻く(服で上腕が圧迫されないように)。
- カフと心臓の高さを合わせる。
- 測定の前に、タバコ、飲酒、カフェインは摂取しない。
- 食後1時間以上あける。
まずは、左右どちらで測るかを決めましょう。最初に測る時に、両方を測ってみて左右差がない場合には、左右どちらで測っても問題ありません。逆に何度測っても、左右差が10mmHg以上ある場合には、左右差ありと判断します。血圧の管理や治療の指標にする場合には、高い側の血圧を参考に。
左右差がない場合には、どちらでも良いのですが、決まった腕で測った方が良いでしょう。
血圧を測定する時には、自宅では静かな場所を選ぶようにしてください。病院などでは場所は選ぶことができませんが、測定する時におしゃべりをしていると、正しい値が出ません。
しっかり服の袖をまくって直接カフ(腕に巻きつけるところ)を巻くのが望ましい測り方です。厚手の服をたくしあげて、カフを巻く上側(二の腕の体に近い部分)が圧迫されている場合には、うまく測定できませんのでご注意ください。

カフを巻いている腕と心臓の高さが合わない場合も、正常に測れません。心臓よりカフが高すぎると、血圧が低くなり、カフが低すぎると血圧が高く測定されてしまいます。
血圧測定の前に、タバコ、飲酒、カフェインを摂取すると血圧に影響がでるため、気をつけましょう。
血圧の治療中の患者様で血圧手帳を記入している場合には、薬の服薬時間と血圧測定タイミングも重要です。できる限りその情報も一緒に記載しましょう。
また、食後に低血圧になる、食事性血圧低下がみられることもあります。食後に測る場合には1時間以上空けるなどの工夫が必要です。
血圧に左右差がみられる場合考えられる原因とは?
通常、血圧の左右差はほぼありません。腕での血圧は、右上腕動脈の圧を測っていることになり、左腕は左上腕動脈です。
心臓から右上腕動脈までの経路は、心臓-上行大動脈-腕頭動脈-右鎖骨下動脈-右上腕動脈。左は、心臓-上行大動脈-左鎖骨下動脈-左上腕動脈です。
この経路の血管の内側や太さ、血管の弾力性などが正常の場合には、左右の上腕動脈までの距離はほぼ同じですので(若干右の方が短い)、大きな差は生じません。
ただ、血管の内側に異常があって内径が狭かったり、血管の弾力性が低下してしまったりした場合には、血圧の左右差が生じます。

明確な定義はありませんが、上の血圧(収縮期血圧)が20mmHg以上、下の血圧(拡張期血圧)が10mmHg以上の差があった場合、左右差ありと判断します。
また、左右差が15mmHg以上の場合には、心臓や血管系の病気が起こるリスクファクターとされています3) 。
 院長 藤田
院長 藤田左右差がでる具体的な病気をみていきましょう。
<左右差がでる具体的な病気>
- 大動脈解離
- 大動脈炎症候群(高安動脈炎、巨細胞性動脈炎)
- 大動脈や鎖骨下動脈の動脈硬化
などがあげられます。
大動脈解離
まずは、大動脈解離4) 。
血圧の左右差がすぐに大動脈解離につながるわけではありません。大動脈解離の多くは、胸や背中の痛み、意識消失などの症状を伴ったりする重篤な病気です。ただ、血圧の左右差がある場合には、必ず鑑別する病気ですので、一番初めにご紹介します。
血管は、動脈も静脈も、内膜、中膜、外膜の3層構造をしています。動脈の中でも、特に大動脈、腕頭動脈、鎖骨下動脈などは、中膜が発達し厚みがあります。大動脈解離は、この中膜が2層に剥がれて、大動脈の内腔が2腔になってしまう病気です。

大動脈解離の原因は、実はまだ全て解明されていません。高血圧などが原因で中膜の強度が弱くなることや、Marfan症候群という遺伝性に中膜などの結合組織と呼ばれる場所が弱くなる基礎疾患があり、さらに大動脈のずり応力(ずれる力)や血管にかかる物理的な力などが原因とされています。
大動脈解離が起こると、大動脈の中での血液の流れがガラリと変わるため、急激に病状が変化し、症状はとても多彩です。主に、血管の破裂と臓器の血流低下が起こります。
心臓近くで起こった解離の場合は、血管の破裂により心タンポナーデ(心臓の周りに血液が溜まり、心臓の動きに影響が出る状態)や、胸腔、腹腔への大量の出血となり、致命的な状態に。
臓器の血流低下では、腕頭動脈や鎖骨下動脈に解離が進んだ場合、血圧の左右差が出ます。20~50mmHgくらい大きな差がでることも。
左右差が大きすぎて、上腕動脈やその先の血管の灌流障害を起こすと、手や指先が冷たくなったり、最悪、指先などが壊死したりします。
大動脈解離の治療は、降圧薬や鎮痛薬で血圧を下げ、血管への負担を減らすことと、解離が生じた場所によっては大きな手術が必要に。
大動脈炎症候群(高安動脈炎、巨細胞性動脈炎)
次に、大動脈炎症候群についてご説明しましょう。
大動脈炎症候群は、名前の通り大動脈や大動脈からの枝の比較的太い血管に炎症が起こり、さまざまな症状をひき起こす病気です。
大動脈炎症候群は2014年に指定難病と認定され、現在は高安動脈炎と呼ばれています5) 。日本では女性の20歳前後に発症のピークがあり、毎年新たに300人前後が診断されている病気です。
原因は、遺伝的な要因と、感染などの環境要因が組み合わさって起こる自己免疫の病気であるとされていますが、現在も解明中です。
大動脈や鎖骨下動脈、上腕動脈などの血管の壁で炎症が起こると、血管の内腔が狭くなります。すると、血圧の左右差や腕や手首で拍動を感じない、というような症状が。
その他、首や脳への血管に病変があると、めまいや頭痛などの脳虚血症状、視力障害、足の血管に病変がある場合には、足の皮疹などが特徴的な症状です。
治療は、ステロイドや免疫抑制薬で、炎症を抑える治療を行います。
同じ血管炎の分類の中で、巨細胞性動脈炎という病気がありますが、主に首〜頭にかけての血管に起こる病気で、発症年齢が50歳以上と、高安動脈炎とは発症年齢などが異なります。
巨細胞性動脈炎でも、腕の動脈に病変があれば、血圧の左右差が起こり、巨細胞性動脈炎の治療も、高安動脈炎と同じく、ステロイドや免疫抑制薬を中心とした薬物治療です。
大動脈や鎖骨下動脈の動脈硬化
次に動脈硬化について。
動脈硬化とは、動脈の血管が硬くなってしまう状態で、血管が狭くなったり、詰まりやすくなったりします。年齢とともに動脈硬化は起こりますが、特に喫煙、高コレステロール血症(脂質異常症)、高血圧、肥満、運動不足などが危険因子となり、さらに進行。

動脈硬化のうち、大動脈や鎖骨下動脈などの太い動脈の内側に、粥腫・プラークというものができるのが、粥状動脈硬化(アテローム動脈硬化)と呼ばれます。
動脈の一番内側の内膜に、血液中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)がくっついて、おかゆのようなドロドロの粥状物質が血管内にでき、これが原因で血管の内腔が狭くなり、十分な血液を送れなくなってしまうのです。
この動脈硬化が心臓を栄養する冠動脈に起こった場合には心筋梗塞、脳への血管に起こった場合には脳梗塞を起こし、腕にいく鎖骨下動脈などに起こった場合には、血圧の左右差として現れます。
血圧の左右差のみで、その他全く症状がない場合もありますが、鎖骨下動脈は腕の血管とともに、脳への血管である椎骨動脈と頸動脈の本幹でもあるので、その部位に動脈硬化がある場合には、鎖骨下動脈盗血症候群を起こすことも6) 。
鎖骨下動脈盗血症候群とは、腕を動かすなどの上肢運動をすると、腕への血流が増える代わりに、椎骨動脈など脳への血流が相対的に少なくなってしまい、めまいや一過性に意識を失うなどの脳虚血症状が起こる病気です。まるで、腕に血液を盗まれてしまっているような状態であることから、この名前がついています。
この病気の原因である鎖骨下動脈狭窄のほとんどは、動脈硬化が原因です。また、大動脈のステントグラフト留置など過去に手術歴がある場合には、これが原因で鎖骨下動脈盗血症候群が起こることがあります。腕の症状や脳虚血の症状がある場合には、鎖骨下動脈の狭窄部位に対してステント留置術などの治療が必要に。
血圧の左右差がみつかった時にできること
血圧は、測る時間やタイミングなどで多少ばらつくことはありますが、左右差はほとんどありません。
左右差が5-10mmHg前後程度であれば気にしなくても問題ないことがほとんどです。また、10-15mmHg以上で常に左右差がある場合にも、即異常というわけではありません。
左右差のみで、腕や手のだるさ、冷えなど他の症状が全くない場合もあります。ただ、血圧の左右差がでる病気には、血管の内側の解離や狭窄などの異常があることが多く、また動脈硬化を見つけるひとつの手段にもなります。
 院長 藤田
院長 藤田左右差がある場合は、症状があってもなくても、そして、左右差があって、高い方の血圧が上の血圧135mmHg以上、下の血圧85mmHg以上の場合は、循環器内科にご相談ください。
まとめ
血圧の左右差について解説いたしました。
多少の左右差は気にしなくても問題ありませんが、何度測っても10-15mmHg以上の差がある場合などは、ぜひ医療機関でご相談ください。
あまり普段血圧を測っていない方は、一度左右の腕の両方を測ってみて左右差がないか、チェックしてみてはいかがでしょうか。
参考文献
1) 高血圧治療ガイドライン2019. 2019年.
2) 長谷部直幸:1.血圧の正しい測定法とこれからの診察室血圧.日内会誌. 100(2):343-350, 2011. https://doi.org/10.2169/naika.100.343
3) Clark CE, et al: Association of a difference in systolic blood pressure between arms with vascular disease and mortality: a systematic review and meta-analysis.
Lancet. 379(9819):905-914, 2012. doi: 10.1016/S0140-6736(11)61710-8.Epub 2012 Jan 30.
4) 2020年改訂版大動脈瘤・大動脈解離ガイドライン. 2020年.
5) 血管炎症候群の診療ガイドライン(2017年改訂版). 2018年.
6) 末梢閉塞性動脈疾患の治療ガイドライン(2015年改訂版). 2015年.