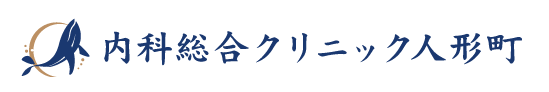院長 藤田
院長 藤田こんばんは。内科総合クリニック人形町 院長の藤田英理です。
食物アレルギーと聞くと、こどもに見られるアレルギーを思い浮かべる方が多いかと思います。食物アレルギーの発症時期は小児期のほうが多いですが、大人になっても発症することが。
また、実際に食物アレルギーを持っていても、アレルギーとは気がつかずに放置されている方も。
食物アレルギーは症状が軽い場合もありますが、重い症状だと呼吸困難や強い吐き気がでることもあります。ですから、食物アレルギーを疑ったらきちんと診断して原因食物を適切に回避することが必要です。
病気を診断する時、多くの病気は症状や検査を組み合わせて診断。例えば、インフルエンザウイルスやコロナウイルス感染症が疑われる時は、ウイルスの検査、肺炎が疑われるときはレントゲンを撮るといったことはイメージがわきやすいかと思います。
しかし、食物アレルギーの場合、自分が「食物アレルギーの可能性があるかも?」と思っても実際にどのような検査をして診断されるかを知っている方は少ないのではないでしょうか。
食物アレルギーを診断する際、血液検査をすることが多いですが、それ以外の検査方法もあり、食物を食べたり除去したりすることで判断することも。
今回は、食物アレルギーについて疑われる症状、そして食物アレルギーを疑った場合にどのような検査が行われるかについて解説していきます。
食物アレルギーの診療の流れを把握しておくと、医療機関を受診する時に役立つと思いますのでぜひごらんになってください。
食物アレルギーとは
 院長 藤田
院長 藤田食物アレルギーは、特定の食物を摂取することが原因となって免疫が過剰に働いてしまい、じんましん・喉の違和感・咳・呼吸困難感・腹痛・嘔吐など体に不利益な症状が出現することをいいます。
通常、私たちは食物からエネルギーを得ており、体は食べ物を異物として認識しません。そのため、食べ物を体から排除しようとする仕組み(免疫反応といいます)は働かずにそのまま消化・吸収。免疫反応はウイルスや細菌といった病気を引き起こすものの侵入を防ぐために必要なメカニズムです。
しかし、食物アレルギーの場合は、本来起こらないはずの食物に対して免疫反応が起こってしまいます。
食物に含まれるたんぱく質が、腸で吸収される際に体がたんぱく質を異物(敵)と認識し、体から排除しようと免疫反応が起こるのです。この過剰な免疫反応がさまざまな症状を生じます(アレルギー反応といいます)。
頻度
食物アレルギーの患者さんは、日本ではどれくらいいるのでしょうか。子どもの食物アレルギーは比較的頻度が多く、乳児が7.6-10%、 2歳児が 6.7%、 3歳児が約5%、小学校以降が1.3-4.5%。
大人の食物アレルギーの正確な頻度ははっきりしない部分もありますが、小学校以降の学童期とそれほど頻度は変わらず、1-2%程度であると考えられています1-5)。
原因食物
食物アレルギーを引き起こす原因食物は、年齢によって異なります。年齢別に新たに食物アレルギーと診断される原因食物の順位は以下の通りです。みていただくとわかるのですが、子どもと大人では原因食物が異なります。
新たに食物アレルギーと診断される原因食物(文献6より引用改変)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| 0歳 | 鶏卵(55.6%) | 牛乳(27.3%) | 小麦(12.2%) | ||
| 1-2歳 | 鶏卵(34.5%) | 魚卵(14.5%) | 木の実(13.8%) | 牛乳(8.7%) | 果物(6.7%) |
| 3-6歳 | 木の実(32.5%) | 魚卵(14.9%) | 落花生(12.7%) | 果物(9.8%) | 鶏卵(6.0%) |
| 7-17歳 | 果物(21.5%) | 甲殻類(15.9%) | 木の実(14.6%) | 小麦(8.9%) | 鶏卵(5.3%) |
| 18歳以上 | 甲殻類(17.1%) | 小麦(16.2%) | 魚類(14.5%) | 果物(12.8%) | 大豆(9.4%) |
次の表は、気がつかずに誤って食べてしまう(誤食)ことでアレルギー症状を引き起こしてしまう原因食物の順位となります。先ほどの表とは若干違うことがわかります。小麦のように食卓でも多く認めるものや、甲殻類などは食物そのものを食べなくてもエキスが入っていて、気がつかずに食べてしまうことも多いので注意が必要です。
誤食により症状が出現する原因食物(文献6より引用改変)
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| 0歳 | 鶏卵(52.1%) | 牛乳(31.3%) | 小麦(11.7%) | ||
| 1-2歳 | 鶏卵(41.4%) | 牛乳(37.7%) | 小麦(14.0%) | ||
| 3-6歳 | 牛乳(29.9%) | 鶏卵(26.5%) | 小麦(16.2%) | 木の実(10.1%) | 落花生(9.5%) |
| 7-17歳 | 鶏卵(21.9%) | 牛乳(21.4%) | 落花生(14.3%) | 木の実(12.5%) | 小麦(8.0%) |
| 18歳以上 | 小麦(19.2%) | 甲殻類(13.5%) | そば(10.6%) | 木の実(8.7%) | 牛乳(6.7%) |
症状
食物アレルギーにはいくつかのタイプがあります。今回は、典型的で一般的に知られている即時型食物アレルギー(原因食物摂取後の2時間以内にアレルギー症状が出現するアレルギー)の症状についてお話します。
食物アレルギーは、摂取した食物を異物と認識し、免疫反応が過剰になることで症状が出現。免疫反応は体の至るところで起こるため、アレルギー症状は全身に認められます。
症状の現れる場所別に、どのような症状が出現するかを以下にまとめました。
- 皮膚症状
じんましん、赤み、かゆみ、湿疹、むくみ - 粘膜症状
目の充血、涙目、口の中・唇・舌の違和感や腫れ - 呼吸器症状
くしゃみ、鼻水、せき、呼吸困難、ゼーゼー、ヒューヒューする(喘鳴と言います)、喉が締め付けられるような感じになる - 消化器症状
嘔気、嘔吐、腹痛、下痢、血便 - 神経症状
元気がない、ぐったりしている、意識がもうろうとしている、失禁 - 循環器症状
血圧低下、唇や爪が青白くなる(チアノーゼといいます)、手足が冷たくなる、脈が速くなったりゆっくりになる、脈が乱れる(不整脈)
このように、アレルギー症状にはいろいろな症状があります。これらの症状の中で、最も多いのが皮膚症状で全体の9割ほどを占めます。アレルギー症状が出現するときは、単独の症状だけのこともありますし、他の症状が同時にまたは遅れて出現することもあります。
食物アレルギーの検査方法
皆さん食物アレルギーはどのように診断されるかご存じでしょうか。何となく「食べ物を食べた後に調子が悪くなるから、この食べ物にアレルギーがあるな」と思う方もいらっしゃると思います。自分で食物アレルギーと判断する方もいるようです。
しかし、食物アレルギーの自己判断は注意が必要。食物を摂取した後に症状がでたからといって、必ずしもアレルギーとは限らないのです。
また、ある食物を食べた後に症状がでた場合に、どの成分がアレルギーなのか判断するのは容易ではありません(例えばくるみ入りのパンを食べた場合は小麦、くるみ、牛乳などが含まれています)。
では、食物アレルギーはどのように診断されるのでしょうか。食物アレルギーは、医療機関によって多少異なるところもありますが、以下のような流れで診断されます。
食物を摂取して症状が出現
↓
医療機関で詳細な問診(疑われる原因⾷物、摂取した後の症状と出現時間、既往歴、アレルギー疾患の家族歴、内服薬、症状と運動・化粧品・ラテックス製品使用と関連があるかなど)
↓
特異的IgE抗体検査や皮膚プリックテスト(時に食物除去試験)
↓
原因食物を特定する。特定できなければ食物負荷試験を行う
↓
食物アレルギーの診断
 院長 藤田
院長 藤田食物アレルギーの診断には検査が欠かせません。ここでそれぞれの検査について解説していきたいと思います。
血液検査(IgE抗体測定)
食物アレルギーの検査で一番イメージされるのが血液検査ではないでしょうか。アレルギーの血液検査で測定されるのはIgE抗体というものです。IgE抗体検査には「非特異的IgE抗体検査」と「抗原特異的IgE抗体検査」があります。
ここで、IgE抗体という少し聞き慣れない言葉がでてきました。アレルギーの話をする上でIgE抗体は非常に重要な箇所なので解説しましょう。
IgE 抗体は、免疫グロブリン(英語でImmunoglobulinと良い、Igと略されます)という血液中に含まれるタンパク質の一種です。免疫グロブリンはIgA、IgD、IgE、IgM、IgGなどさまざまな種類があり、免疫グロブリンの中でIgEはアレルギーの発症に深く関わっています。
食物アレルギーの発症のメカニズムは以下の通りです。
① アレルギーとなる食物(アレルゲン)を摂取。
② 摂取したアレルゲンに対するIgE抗体(抗原特異的IgE抗体)が作られ、IgE抗体は皮膚や粘膜に存在するマスト細胞と結合(感作といいます)。
③ 感作された後にアレルゲンとなる食物を摂取すると、IgE抗体がアレルゲンを捕まえ。
④ IgE抗体がアレルゲンを捕まえると、マスト細胞からヒスタミンやロイコトリエンなどの化学伝達物質が放出。
⑤ 化学伝達物質によってアレルギー症状が誘発。
ここでIgE抗体検査のお話に戻ります。
IgE抗体検査には「非特異的IgE抗体検査」と「抗原特異的IgE抗体検査」がありますが、食物アレルギーの診断には、抗原特異的IgE抗体検査です。
非特異的IgE抗体検査は、個別のIgE抗体ではなく、全てのIgE抗体の量を測定するもので、簡単に言えばアレルギー体質であるかどうかの目安になるもの。
血中抗原特異的IgE抗体検査は個別のアレルゲン(食物アレルギーでは食べ物です)についての血液内のIgE抗体量を測定。測定された数値は7段階(クラス0-6)にクラス分けされ、IgE抗体量が多い(クラスが高い)ほどアレルギー症状が起きやすいと考えられます。
血中抗原特異的IgE抗体検査は、食物アレルギーを診断する上で重要な検査方法です。そして、特定の食物に対するIgE抗体が高ければ、その食物を摂取するとアレルギー症状が出現する可能性が高い状態といえます。
しかし、IgE抗体の値が高いからといって必ず症状がでるというわけではありません。この点は誤解のないよう、よく注意しましょう。
実際に、血中抗原特異的IgE抗体検査で抗体の数値が高くても、症状がでないということも比較的よく見られます。
もう一つ気をつけたいことは、特異的IgE抗体の数値とアレルギー症状は相関しないということです。例えば、特定の食物の抗原特異的IgE抗体の数値がクラス6と非常に高かった場合も、摂取後にアレルギー症状が強く出るということとは直接関係ありません。
血中抗原特異的IgE抗体検査は、アレルギー症状を発症させる原因食物を推測することができる有用な検査です。しかし、この検査のみで食物アレルギーと診断することはできません。
抗体の数値によって症状の重症度を予測することはできないので解釈に注意が必要なのです。
 院長 藤田
院長 藤田結果をみてご自身で食物アレルギーか自己判断するのは控えて医療機関で相談しましょう。
抗原特異的IgE抗体検査で陽性と判定されたが、これまで食べたことがあって症状がない場合の対応は?
血中抗原特異的IgE抗体検査でよく聞かれる質問です。ぜひ理解していただきたいので取りあげました。
 院長 藤田
院長 藤田結論から申し上げると、症状がなければこれまで通り食べても問題ありません。
先ほども述べたように、
血中抗原特異的IgE抗体が陽性=食物アレルギー
ではありません。食物アレルギーは、ある特定の食物を摂取した後にアレルギー症状がでて、IgE抗体が陽性の場合のことを言います。仮にIgE抗体が陽性であっても、症状が出なければ通常摂取に問題はないと考えていただいて結構です。
抗原特異的IgE抗体検査で陰性と判定されたが、これまで食べたことがあってその食物を食べた後に症状が出現する場合の対応は?
先ほどの質問とは逆の内容となります。こちらに関しては、症状がある場合はその原因食物の除去が必要になるかと思います。
確定診断には、後述する食物経口負荷試験を実施。負荷試験でしっかりと症状が出現するにもかかわらず血中抗原特異的IgE抗体が陰性のこともあるので、時期をあけたり、他の方法で検査することもあります。
食物アレルギーの診断は、症状の有無が一番大切ですのでIgE抗体の陽性/陰性にかかわらず、症状がでたら食物アレルギーとして除去する必要が。
皮膚プリックテスト
血中抗原特異的IgE抗体検査以外のアレルギー検査として、皮膚テストがあります。皮膚テストは皮膚からアレルゲンを滴下し、アレルゲンと皮膚の下にあるマスト細胞(アレルギー症状に関与する細胞)を反応させてその反応の強さをみる検査です。
皮膚テストには、プリックテスト、スクラッチテスト、皮内テストなどが。スクラッチテストは検査をする人の手技によって結果が異なることがあり、皮内テストは重症なアレルギー症状であるアナフィラキシーを起こすリスクがあるため、現在はプリックテストが主に用いられています。
 院長 藤田
院長 藤田ここではプリックテストについて解説していきます。
プリックテストは、アレルゲンのエキスを滴下し、専用の針(プリック針)で皮膚の表面に微細なキズをつけて、アレルギー反応を調べる検査です。アレルギーがある場合には、発赤したり、膨らんできます(陽性判定)。また、エキスではなく、食物にプリック針を刺して、そのまま皮膚に刺すプリック to プリック テストを行うことも。
プリックテストは外来で簡単に行うことができ、短時間(15分)で結果が出て、安全性も高い検査です。
プリックテストは血中抗原特異的IgE抗体と同じく、アレルゲンにIgE抗体が反応するか(感作されているか)をみる検査。結果は間接的に特異的IgE抗体の存在を示しているものなので、血液の特異IgE抗体の検査と同様に、結果のみですぐには診断せず、補助的な検査となります。
プリックテストは簡単にしかも安全に行うことができる検査ですが、注意点があります。
① 抗ヒスタミン薬の内服
プリックテストは、感作されているかを皮膚症状の有無で判断します。もし抗ヒスタミン薬を飲んでいる場合は本当にアレルギー症状があったとしても薬の効果で出現しない可能性が(本当は陽性なのに薬の効果で陰性と判断されてしまうということ)。
そのため、抗ヒスタミン薬を内服している方はプリックテスト前に3日以上休薬する必要があります。
② 機械性蕁麻疹(きかいせいじんましん)
プリックテストは、専用の針で皮膚の表面に微細なキズをつけて、アレルギー反応を調べます。アレルギーの中でも針などの刺激で蕁麻疹(じんましん)がでてしまう機械性蕁麻疹の方がいます。
機械性蕁麻疹の方は食物アレルギーでなくても針の刺激で蕁麻疹が出てしまうため、誤って陽性と判断されてしまう可能性が。そのためプリックテストを行う際はアレルゲンのエキスだけなく、生理食塩水などアレルゲンとならないものを滴下して針をさし、その部分の反応と比較することが大切です(陰性コントロールと呼ばれます)。
食物除去試験
食物アレルギーが疑われる原因食物を除去することで、アレルギー症状が出現しなくなるかを確認する検査です。具体的には、疑われる原因⾷物を1-2週間ほど除去し、症状の有無を確認します。
食物除去試験はアトピー性皮膚炎の原因に食物アレルギーが関与しているか調べるために行われることが。食物除去試験を行い、症状が出現しない、もしくは皮膚症状が改善したら、除去した食物が本当に原因なのか確定するために次に紹介する食物負荷試験を行います。
食物負荷試験
食物経口負荷試験は、英語でOFC(oral food challengeの略)とも呼ばれ、アレルギーが確定もしくは疑われる食品を1回〜数回に分けて摂取し、アレルギー症状が出現するかどうかをみる検査です。
食物経口負荷試験は最も確実な診断方法となり、検査目的は主に以下となっています。
食物経口負荷試験の目的
- 食物アレルギーの確定診断(原因アレルゲンの同定)
1)食物アレルギーを起こした原因として疑われる食物の診断
2)感作されているが、未摂取の食物の診断
3) 食物アレルギーの関与を疑うアトピー性皮膚炎の病型で除去試験により原因食物として疑われた食物の診断 - 安全に摂取可能な量の決定および耐性獲得の診断
1) 安全摂取量の決定
2) 耐性獲得の確認
(文献7より一部改変)
食物経口負荷試験を行う前に
食物経口負荷試験はさまざまな目的で行われますが、皮膚の所見で判断するプリックテストと比較して直接経口摂取するので、リスクはプリックテストより高めです。したがって、試験を行う前には確認すべき注意点があります。
- 体調が万全の状態で行うようにしましょう。
アレルギーは体調不良の場合、症状が出やすくなってしまうことがあり、アレルギー症状が強くでてしまうリスクがあります。また、風邪を引いていたり、胃腸炎で症状があると負荷試験中の症状がアレルギー症状によるものか、病気の症状によるものか判断が困難になることが。 - 他のアレルギー疾患がきちんとコントロールされた状態で行いましょう。
食物アレルギーをもつ方は、花粉症、アトピー性皮膚炎、気管支喘息など他のアレルギー疾患を合併していることがあります。疾患のコントロールが不良だと、負荷試験中の症状が食物アレルギー以外のアレルギー疾患によるものか判断が困難になったり、負荷試験中に思わぬ強いアレルギー症状が出現してしまうことが。
経口負荷試験の方法
食物経口負荷試験は、食物アレルギーが疑われる食物を1回の摂取(単回摂取)もしくは2-3回に分けて摂取し行われます。複数回に分けて行う方法では、摂取間隔は30-60分あけることが望ましく、最終摂取から2時間以上経過をみてアレルギーの有無を判定。
食物経口負荷試験中に気をつける症状
食物経口負荷試験の判定は、食物を摂取して症状が出現するかしないかによって行われます。具体的にどのような症状をみていくのか解説します。
「食物アレルギーとは」で述べたように、アレルギー症状にはさまざまなものがあります。実際負荷試験を行っていても、症状がアレルギー症状によるものか判断が困難なことがあります。
事前にアレルギー症状として起こりうるものを知っておくと、負荷試験で症状が出た際に、アレルギーによるものか推測できます。その結果、正しい判定につながりますのでぜひ参考にして下さい。
| グレード1 (軽症) | グレード2 (中等症) | グレード3 (重症) | |
| 紅斑・蕁麻疹・膨疹 | 部分的 | 全身症 | ← |
| 掻痒(かゆみ) | 軽いかゆみ(自制内) | かゆみ(自制外) | ← |
| 口唇、眼瞼腫脹 | 部分的 | 顔全体の腫れ | ← |
| 口腔内、咽頭違和感 | 口、のどのかゆみ、違和感 | 咽頭痛 | ← |
| 腹痛 | 弱い腹痛 | 強い腹痛 | 持続する強い腹痛 |
| 嘔吐・下痢 | 嘔気、1回の嘔吐・下痢 | 数回の嘔吐・下痢 | 繰り返す嘔吐、 便失禁 |
| 咳嗽、鼻汁、鼻閉、くしゃみ | 間欠的な咳嗽、 鼻汁、鼻閉、くしゃみ | 断続的な咳嗽 | 持続する強い咳、犬吠様咳嗽 (かすれ声) |
| 喘鳴、呼吸困難 | – | 聴診で喘鳴、 軽い息苦しさ | 明らかな喘鳴、呼吸困難、チアノーゼ、嚥下困難など |
| 頻脈、血圧 | – | 頻脈、血圧軽度 低下、蒼白 | 不整脈、血圧低下、心停止など |
| 意識状態 | 元気がない | 眠気、軽度頭痛、恐怖感 | ぐったり、不穏、 失禁、意識消失 |
食物経口負荷試験の判定
食物経口負荷試験の方法について説明しましたが、判定については食物摂取後の症状により、行われます。
判定は陽性、判定保留、陰性の3つに分けられ、それぞれの判定基準は以下の通りです。
- 陽性
負荷試験で摂取し数時間以内に明らかなアレルギー症状が出現した場合は陽性と判断され、食物アレルギーと確定診断されます。 - 判定保留
軽い症状(グレード1)や主観的で判断しにくい症状の場合は1回の試験では判定できないことがあり、判定保留とされます。
判定保留とされた場合は、日を改めて再度負荷試験を行う、または自宅で何回か摂取して症状が再度出現するか確認。 - 陰性
負荷試験中に症状が出現しなかった場合は陰性と判定されます。しかし、自宅でも負荷試験で摂取した量を何回か摂取し、症状が出現しないことを確認。そして確実に摂取できることが確認されて最終的に陰性となります。
食物経口負荷試験は食物アレルギーの確定診断となる検査ですが、アレルギーの原因が疑われる食物を直接経口摂取するので他の検査と比べて症状が出現するリスクがどうしても高くなります。そのため、医療機関で摂取や症状が出現してもすぐ対応できるような準備が必要です。
食物経口負荷試験は医師の指示なく、自己判断で自宅で行うことは極めて危険ですので、控えましょう。
抗原特異的IgG抗体検査について
最近は少し減ってきたかなという印象があるのですが、インターネット等で食物に対する「抗原特異的IgG抗体検査」が食物アレルギーの診断に有用であるとされる情報がたまに見られます。
抗原特異的IgG抗体検査は、遅発型の食物アレルギーの診断に有用です。遅発型アレルギーでは、慢性的に続くアレルギー症状(疲労、蕁麻疹、下痢、頭痛)を示し、IgG抗体を調べることで診断し、その食物を除去することで症状が改善するとされています。
しかし、この検査はいくつか注意すべき点があります。実際に抗原特異的IgG抗体検査は、アメリカやヨーロッパ学会、日本アレルギー学会、日本小児アレルギー学会でも食物アレルギーの診断として推奨はしていません、その理由として以下の4つをあげています8) 。
- 食物抗原特異的IgG抗体は食物アレルギーのない健常な人にも存在する抗体である。
- 食物アレルギー確定診断としての負荷試験の結果と一致しない。
- 血清中のIgG抗体のレベルは単に食物の摂取量に比例しているだけである。
- このIgG抗体検査結果を根拠として原因食品を診断し、陽性の場合に食物除去を指導すると、原因ではない食品まで除去となり、多品目に及ぶ場合は健康被害を招くおそれもある。
 院長 藤田
院長 藤田もう一つ気をつけたい事は、抗原特異的IgG抗体検査は健康保険適用の検査ではなく、自費での検査だということです。
食物アレルギーの検査を受ける場合は、医療機関で正しい検査を受けるようにしましょう。
まとめ
今回は食物アレルギーについて疑われる症状、そして食物アレルギーを疑った場合にどのような検査をして診断されるかについてお話しました。
食物アレルギーの検査は、血中抗原特異的IgE抗体検査やプリックテスト、食物除去試験など多岐にわたりますが、確定診断として経口負荷試験が行われます。
血中抗原特異的IgE抗体検査や、プリックテストは、その検査だけで診断することはありませんが、食物アレルギーが疑われるかの参考となる有用な検査です。
検査結果の解釈に戸惑ってしまうことがよく見受けられます。本文でも述べましたが、症状の出現の有無が一番大切な指標です。
食物アレルギーが疑われる時はご自身で判断、経口負荷試験を行うことはしないで医療機関で専門の医師と相談しながら検査、診断を進めていくようにしてください。
食物アレルギーの検査について理解し、適切な診断につながる助けになれば幸いです。
この記事を書いた人

内科総合クリニック人形町 院長
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医
東京大学医学部保健学科および横浜市立大学医学部を卒業
東京大学付属病院や虎の門病院等を経て2019年11月に当院を開業
最寄駅:東京地下鉄 人形町駅および水天宮前駅(各徒歩3分)
参考文献
1) Ebisawa M, et al. Prevalence Of Allergic Diseases During First 7 Years Of Life In Japan. J Allergy Clin Immunol 125(2):AB215, 2010. DOI:10.1016/j.jaci.2009.12.841
2) Yamamoto-Hanada K, et al. Allergy and immunology in young children of Japan: The JECS cohort. World Allergy Organization J 2020 Nov 7;13(11):100479. doi: 10.1016/j.waojou.2020.100479.eCollection 2020 Nov.
3) 柳⽥紀之ら.厚生労働省「平成27年度子ども・子育て支援推進調査研究事業」保育所入所児童のアレルギー疾患罹患状況と保育所におけるアレルギー対策に関する実態調査結果報告. アレルギー 67:202-210, 2018
4) 今井孝成ら. 学校給食における食物アレルギーの実態. ⽇本⼩児科学会雑誌109:1117-1122, 2005
5) 日本学校保健会. 平成25年度学校⽣活における健康管理に関する調査事業報告書 2014. https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H260030/H260030.pdf
6) 今井孝成ら. 消費者庁「食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業」 平成29(2017)年即時型食物アレルギー全国モニタリング調査結果報告. アレルギー 69: 701-705, 2020
7) 食物アレルギー研究会. ⾷物経⼝負荷試験の⼿引き2020.
https://www.foodallergy.jp/manual-ofc2020/
8) 日本アレルギー学会. 〔学会見解〕血中食物抗原特異的IgG抗体検査に関する注意喚起. https://www.jsaweb.jp/modules/important/index.php?content_id=51