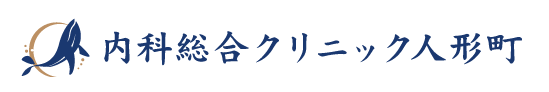糖尿病の患者さんの治療は、大きく①食事療法、②運動療法、③薬物療法の3つに分けられます。通常、薬物療法は、食事療法や運動療法を行っても血糖コントロールが安定しない場合に、追加治療として行われます。
糖尿病の治療と聞くと、薬物療法を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。しかし、糖尿病患者さんにおける治療の基本は、「食事療法と運動療法」です。
薬物療法を始めれば食事と運動をしなくていいというのではなく、薬物療法を開始した後でも食事療法と運動療法の両方を継続していく必要があります。
今回は、糖尿病の薬物療法について、どのようなお薬があるのか、それぞれの薬の特徴や注意すべき点について解説していきます。少しでも皆さんのお薬の理解にお役立ていただければと思います。
この記事の執筆者

藤田 英理 内科総合クリニック人形町 院長
東京大学医学部保健学科、横浜市立大学医学部を卒業。虎の門病院、稲城市立病院、JCHO東京高輪病院への勤務を経て内科総合クリニック人形町を開院。総合内科専門医。AGA治療や生活習慣病指導も行う。
糖尿病治療の3本柱
 院長 藤田
院長 藤田糖尿病の治療は、①食事療法、②運動療法、③薬物療法の3つの治療方法があります。これからそれぞれの治療方法について解説。
食事療法
食事療法は、糖尿病の治療の中でも最も基本となる治療方法です 。
糖尿病は生活習慣が大きくかかわっており、食事の内容を見直すことは大切。
意外に思うかもしれませんが、糖尿病の患者さんで絶対食べてはいけないというものはありません。食事療法のポイントは炭水化物、たんぱく質、脂質の三大栄養素のバランスと患者さんの年齢、活動量に基づいて1日の総摂取カロリーを考え、それに合わせた食事をすることです。
その他に、規則正しい食習慣を守ることも重要。いくら1日の総摂取カロリーを守っていても、朝ご飯をぬいたり、夜遅くに食事をする、1度の食事でたくさんの量を食べるようなことがあると血糖値が急に上がったり、太りやすくなるのでせっかくの食事療法の効果が半減してしまいます。
食事療法を行うときは、「摂取カロリーを守ってバランスのとれた食事をとる」「1日3食規則正しく食べるようにする」「1回の食事量が偏らないようにする」「夜遅くに夕食をとらないようにする」などの工夫が必要です。
どのような食品を選ぶといいのか、という点ですが、日本糖尿病学会から「糖尿病食事療法のための食品交換表」が発行されていて、病院の栄養指導でよく用いられています。また、外食やテイクアウトを利用される際はホームページなどで栄養成分が公表されていることもありますので、参考にしてみるといいでしょう。
運動療法
運動療法は、食事療法と並び糖尿病患者さんにとって大切な治療方法です。運動療法にはたくさんのメリットがあります。
具体的には、「運動自体が血糖値を低下させる」「運動によるエネルギー消費、肥満の改善」などがあげられます。最も重要なメリットは「運動することで糖尿病によって低下しているインスリンの働きが改善する(インスリンの効きがよくなる=インスリン抵抗性が改善する)」ことです。
その他にも、筋力の維持、骨粗鬆症の予防、体を動かすことによるストレス解消といった効果も期待できます。そのため、継続できるような無理のない範囲の運動をするとよいでしょう。
では、運動療法にはどのようなものがあるのでしょうか。大まかに分けると、①有酸素運動と②レジスタンス運動(筋肉に負荷をかける運動)が。
糖尿病患者さんは、有酸素運動のほうがより望ましいと言われています。その理由として、運動療法の最大のメリットである「運動することで糖尿病によって低下しているインスリンの働きが改善する」効果は、有酸素運動によってもたらされるからです。
年齢や糖尿病の状態、および他の病気がある場合は、無理な運動をすると、かえって状態が悪化することもありますので運動をしていいのか、どれくらい運動してもいいのかを病院で相談してから行うようにしましょう。
薬物療法
 院長 藤田
院長 藤田薬物療法は、食事療法や運動療法を行っても、十分な血糖コントロールが達成できない場合に開始します 。
薬物療法は大きく分けて以下のように分類。
- 飲み薬(経口血糖降下薬)
- 注射薬(インスリン)
- 注射薬(GLP-1受容体作動薬)
患者さんがどの糖尿病のタイプなのか、肥満の有無、インスリンの分泌能力などを総合的に評価して、どのような薬が使われるか決定。
糖尿病の治療は上記の3つを組み合わせて行われます。
重要なポイントは、それぞれの治療方法は独立したものではなく、互いに関係しあっているということです。具体的な糖尿病の種類や程度にもよりますが、まずは食事療法と運動療法を行い、それで改善が乏しいようであれば薬物治療を追加します。
治療の流れ(イメージ)
飲み薬(経口血糖降下薬)
経口血糖降下薬は、主に2型糖尿病の方が対象です。
ご自身の膵臓(すいぞう)からインスリンを分泌する力が残っており(インスリン非依存状態といいます)、食事や運動療法を行っても十分な血糖コントロールが達成できない場合に使用されます。
経口血糖降下薬について理解するためには、まず、2型糖尿病の病態を理解することが大切です。病態を理解することで、そのお薬がどのように働いて効くのかを理解しやすくなります。
<2型糖尿病の病態>
糖尿病は、膵臓から出されるインスリンの作用が不足することで、高血糖状態が続いてしまう病気です。インスリンは食事などで血糖が上昇すると、すい臓から分泌され、ブドウ糖を筋肉などへ送り、エネルギーとして利用されます。
もし、インスリンの作用不足があると、筋肉へ送られる血液中のブドウ糖が減り、高血糖に。血液にブドウ糖がたくさん存在すると、あまったブドウ糖はおしっこにも糖分として出てしまいます。
インスリンの作用が不足する理由は以下の2つです。
- インスリン抵抗性増大:筋肉などでのブドウ糖の取り込みが低下すること。
(つまり、インスリンが効きにくくなる) - インスリン分泌能低下:膵臓から分泌されるインスリンを分泌する力が低下すること。
これらは生活習慣(過食、肥満、運動不足)により引き起こされます。
病態と、それに応じたお薬の作用するポイントを図にまとめたので参考にしてください。
※糖毒性:高血糖状態が続くと、インスリン分泌能やインスリン抵抗性が悪化し、高血糖がさらに増悪する悪循環に陥ることをいいます。
2型糖尿病はさまざまな病態から成り立っていて、いずれも高血糖状態を引き起こします。そして、経口血糖降下薬はそれぞれの病態に作用するように作られており、多数の種類が。
次に、それぞれの経口血糖降下薬の商品名やどのように血糖を低下するのかという簡単な作用機序と、特徴、副作用を理解していただく表をまとめました。
<インスリン抵抗性を改善する薬>
| 種類(主な商品名) | 作用機序 | 特徴・効果・副作用 |
|
ビグアナイド薬 (メトグルコ) |
肝臓で糖をつくる働きを抑制 →筋肉などでブドウ糖の利用を促して血糖値を下げる。 |
低血糖のリスクは少ない 副作用:食欲不振、悪心、下痢など。 心、肝、腎機能障害のある方や高齢者は乳酸が増えて、血液が酸性になる乳酸アシドーシスになる可能性がある。 |
|
チアゾリジン薬 (アクトス) |
脂肪や筋肉でインスリンの効きをよくして、血液中のブドウ糖の利用を増やして血糖値を下げる。 |
インスリン抵抗性を改善させる。 副作用:水分貯留によるむくみや体重増加がみられる方もいる。 |
<インスリンの分泌を促す薬>
| 種類(主な商品名) | 作用機序 | 特徴・効果・副作用 |
|
スルホニル尿素薬:SU薬 (オイグルコン、ダオニール、グリミクロン、アマリール) |
膵臓に働きかけて、インスリンの分泌を促し、血糖値を下げる。 |
インスリン分泌が保たれている方が対象。 血糖低下作用が強く、低血糖に注意。 内服中は体重増加に注意。 |
|
速効型インスリン分泌促進薬:グリニド薬 (スターシス、ファスティック、グルファスト、シュアポスト) |
膵臓に働きインスリンの分泌を促す。SU薬と比べ作用時間が短い。 |
食後高血糖を改善するのによい適応。 SU薬に比べると低血糖になりにくい。 必ず食直前に内服する。 |
|
DPP-4阻害薬 (ジャヌビア、グラクティブ、エクア、ネシーナ、トラゼンタ、テネリア、スイニー、オングリザ、ザファテック、マリゼブ) |
食事摂取で上昇した血糖に応じて膵臓からのインスリンの分泌などを調整して血糖を下げる。 |
食事の影響がなく、食前・食後のどちらの内服でもよい。 単独では低血糖のリスクが低い。 体重増加のリスクが低い。 副作用:胃腸障害 |
|
GLP-1受容体作動薬 (リベルサス) |
膵臓に働きかけて血糖値が高くなると、インスリンの分泌を促し血糖値を下げる。 | これまで注射薬で処方されていたが経口薬も販売された。
低血糖のリスクは少ない。 使い始めに吐き気、下痢、便秘といった胃腸症状があらわれることがある。 |
<糖の吸収や消化をゆっくりにする薬>
| 種類(主な商品名) | 作用機序 | 特徴・効果・副作用 |
|
αグルコシダーゼ阻害薬 (グルコバイ、ベイスン、セイブル) |
小腸でブドウ糖の分解と吸収を遅らせ、食後の血糖上昇を抑える。 |
食後高血糖を改善する。 副作用:腹部膨満感、おならの増加 低血糖時はブドウ糖の内服が必要。 |
<腎臓での糖の再吸収をおさえ、尿へブドウ糖排泄を促す薬>
| 種類(主な商品名) | 作用機序 | 特徴・効果・副作用 |
|
SGLT2阻害薬 (スーグラ、フォシーガ、ルセフィ、アプルウェイ、デベルザ、カナグル、ジャディアンス) |
腎臓のブドウ糖再吸収を抑制し、尿からブドウ糖の排泄を促し、血糖を下げる。 |
低血糖のリスクは少ない。 体重減少効果もある。 副作用:膀胱炎、尿道・膣の感染症や尿量増加による脱水に注意。 |
さらに、比較的新しいお薬で最近処方されることが多くなってきたDPP-4阻害薬とSGLT2阻害薬、配合薬、ツイミーグについて解説を追加します。
DPP-4(ディー・ピー・ピー・フォー)阻害薬
1) 概要
DPP-4阻害薬は、食事摂取時に上昇した血糖値に応じて膵臓からのインスリン分泌を調整して血糖を下げるお薬です。
DPP-4阻害薬は、インクレチンを分解する酵素であるDPP-4の働きを阻害することで、インクレチンの効果を長持ちさせてインスリンを増やし、血糖を下げます(また血糖をあげるグルカゴンというホルモンの分泌も抑制)。
※インクレチン:食事をとると小腸から分泌されるホルモンのことをインクレチンといいます。インクレチンにはGLP-1とGIPがありますが、主にGLP-1の働きが重要です。
インクレチンは、膵臓に働きかけてインスリン分泌を促します。特徴としては、血糖が高いときのみインスリン分泌を促し、血糖が高くないときはインスリン分泌を促しません。そのため、DPP-4阻害薬や、後にお話するGLP-1受容体作動薬は、単独で低血糖になるリスクは低いということになります。
~イメージ~
2) 副作用
副作用として頻度は高くありませんが、嘔気や嘔吐といった消化器症状を起こすことがあります。
SGLT2(エスジーエルティーツー)阻害薬
1) 概要
SGLT2阻害薬は、腎臓のブドウ糖再吸収を抑制し、尿からブドウ糖の排泄を促し、血糖を下げるお薬です。血液の余分な糖分を尿とともに体の外へ排出し、血糖を下げます。
SGLT2は腎臓の近位尿細管という場所に存在。近位尿細管では血液から必要なものを体に取り込みます。そして、不要なものを尿として体の外へ排出。
SGLT2はブドウ糖を体へ取り込む働きをしています。SGLT2阻害薬は、この働きをブロックするため、ブドウ糖が体に取り込まれず、その結果、尿へブドウ糖が排泄され、血糖が低下。
SGLT2阻害薬を内服すると、多量の糖分が尿へ排泄されます。このため吸収されるはずだった糖分が喪失し、カロリーも喪失。糖が喪失されるとエネルギーを脂肪から利用します。
そのため、SGLT2阻害薬は体重減少効果や脂肪減少効果も。
最近SGLT2阻害薬は血糖降下作用だけでなく、腎臓の保護作用や心不全に対する効果も発見されています。
2) 注意点
たくさんの効用のあるSGLT2阻害薬ですが、内服する上でいくつか注意点があり、日本糖尿病学会より適正使用について声明がでています2) 。
要点は以下です。
- 1型糖尿病の方には一定のリスクがあり、インスリン治療をしっかり行っていても血糖コントロールが不良の時のみ使用を検討する。
- 他の薬(SU薬やインスリン)を使用する際は、他の薬の量を調整するなど低血糖に注意する。
- 高齢者への投与は慎重に行う。
- 脱水に注意する(SGLT2阻害薬は尿へブドウ糖を排泄し、尿量も増加)。
- 体調が悪いときや手術前は薬を中止する。
- 倦怠感、嘔気、嘔吐、腹痛がでたときは、血糖が正常でも糖尿病性ケトアシドーシスの可能性もあるので専門医へ相談する。
- 発疹が出現した場合はすぐに中止し、皮膚科へ相談する(薬剤による影響の可能性が)。
- 尿路感染症、性器感染症に注意する(尿にブドウ糖が多くでるため細菌感染にかかりやすい)。
配合薬
経口血糖降下薬はたくさんの種類があり、内服するのも一苦労です。
最近2つの成分が一つの薬に含まれる配合薬も販売されています。
たくさんの錠剤があって飲むのを忘れてしまうときなどは、配合薬を使用するというのも一つの解決手段です。
<配合薬>
| 種類 | 商品名 |
| SGLT2阻害薬+DPP-4阻害薬 |
カナリア配合錠 スージャヌ配合錠 トラディアンス配合錠 |
| ビグアナイド薬+DPP-4阻害薬 |
イニシンク配合錠 エクメット配合錠 メトアナ配合錠 |
| ビグアナイド薬+チアゾリジン薬 | メタクト配合錠 |
| 速効型インスリン分泌促進薬+αグルコシダーゼ阻害薬 | グルベス配合錠 |
| チアゾリジン薬+DPP-4阻害薬 | リオベル配合錠 |
| スルホニル尿素薬+チアゾリジン薬 | ソニアス配合錠 |
ツイミーグ
1) 概要
ビグアナイド薬と構造が似ているお薬で、ミトコンドリアの機能を改善することで効果を発揮する薬といわれています。
ミトコンドリアは、肝臓、筋肉などさまざまな臓器に存在します。細胞の中の小さい構造物ですが、細胞の活動に必要なエネルギーの多くを産生する非常に大切な器官です。
ツイミーグを服用することで、インスリン抵抗性とインスリン分泌能がともに改善。また、肝臓での糖新生(アミノ酸や脂質からブドウ糖をつくること)を抑制することも知られています。
~イメージ~
2) 副作用
なお、ビグアナイド薬に似ていると述べましたが、ビグアナイド薬の副作用である乳酸アシドーシスは起こりにくいとされています。副作用は、1-5%未満の頻度で悪心、下痢、便秘。
注射薬(インスリン)
インスリンは胃で速やかに消化されてしまうため、内服薬での投与は難しく、現時点では注射で投与する必要が。
1) 概要
インスリンは膵臓から分泌されるホルモンで、血糖値を下げる働きがあります。インスリンは胃で速やかに消化されてしまうため、内服薬での投与は難しく、現時点では注射で投与する必要が。
インスリンは、ヒトが生きていくために必要不可欠なホルモンで、インスリンを自分でほとんど作れない1型糖尿病患者さんは、インスリン療法が必要です。
2型糖尿病患者さんにおいても、食事・運動療法に加えて経口血糖降下薬による薬物療法を追加しても血糖コントロールが不良の方は、インスリン療法の適応となります。
最近は、膵臓の負担を減らす目的で、比較的早期にインスリン療法を導入する例も増加。また、2型糖尿病患者さんの手術前や妊婦さんなど経口血糖降下薬が使用できない状況の場合も使用します。
2) 種類
インスリン製剤は非常に多くの種類が。インスリン製剤は、効果が発現する時間や効果が持続する時間によって超速効型、速効型、混合型、配合溶解、中間型、持効型溶解という種類に分けられています。
患者さんの状態や生活スタイルに応じてインスリン製剤を使用。それぞれの製剤の特徴を表にまとめました。
<インスリン製剤>
| 分類 | 商品名 特徴 |
発現時間 | 最大作用時間 | 持続時間 |
| 超速効型 |
ヒューマログ、ノボラピッド、フィアスプ、ルムジェブ、アピドラ、インスリンリスプロ |
10-20分 | 30分-3時間 | 3-5時間 |
| 速攻型 |
ヒューマリンR、ノボリン |
30分-1時間 | 1-3時間 | 5-8時間 |
| 混合型 |
ヒューマログミックス、ノボラピッドミックス、ノボリン30R、イノレット |
10分-1時間 | 30分-12時間 | 18-24時間 |
| 配合溶解 | ライゾテグ 超速効型と持効型溶解を混合したもの |
10-20分 | 1-3時間 | 42時間超 |
| 中間型 | ヒューマリンN、ノボリンN 速効型インスリンにプロタミンを添加して作用時間を長くさせたもの |
1-3時間 | 4-12時間 | 18-24時間 |
| 持効型溶解 |
レベミル、トレシーバ、ランタス、ランタスXR、インスリングラ |
1-2時間 |
3-14時間 ピークがないものも |
24-42時間 |
3) 副作用
インスリン製剤は、血糖を下げるお薬です。そのため、インスリン量が過剰になると低血糖を起こすことが。
具体的な状況としては、①インスリン注射をしたけど、食べる量がいつもより少なかったり、食事のタイミングが遅れた時、②運動をいつもより多くした時、③インスリン量を間違えた時などがあります。
注射薬(GLP-1受容体作動薬)
1) 概要
DPP-4阻害薬の説明の際に少し触れましたが、GLP-1は、食事をとると小腸から分泌されるホルモンであるインクレチンの一つで、血糖が高いときにインスリン分泌を促します。
通常、GLP-1は、DPP-4という酵素によってすぐ分解されてその働きを失ってしまいます。GLP-1受容体作動薬はDPP-4による分解がされにくいような工夫がされているため、体の中にあるGLP-1よりも長時間作用が持続します。
GLP-1受容体作動薬は、膵臓だけでなく、胃や脳に作用して胃の内容物の排泄を抑制したり、食欲を抑制したりする効果もあるため、体重減少につながるとされています。
~イメージ~
2) 種類
注射薬のGLP-1受容体作動薬は、1日1-2回または週1回のものがあります。
ビクトーザ、リスキミア:1日1回
バイエッタ:1日2回
オゼンピック、ビデュリオン、トルリシティ:1週間に一回
3) 副作用
GLP-1受容体作動薬は、単独では低血糖を起こしにくいのですが、スルホニル尿素薬やインスリンを併用している方の場合、低血糖に注意が必要です。また、初期症状で嘔気、下痢、便秘などの消化器症状を引き起こすことがあります。
注射の配合薬
注射にも配合薬があり、インスリンの持効型溶解とGLP-1受容体作動薬をまぜたものがあります。商品名は、ゾルトファイ、ソリクアなどです。
糖尿病薬の正しい飲み方を確認しましょう
糖尿病の飲み薬は非常に多くの種類があり、それぞれ飲むタイミングが異なります。
よく、「薬を飲み忘れたんですけど、今忘れたことに気がついたので飲んでも大丈夫ですか?」「1個前のタイミングのお薬を飲み忘れたんですけど、次の内服の時にまとめて飲んだ方がいいですか?」「ご飯食べないときは、薬を飲まなくても平気ですか?」と質問を受けます。
ここで注意しなくてはいけないのは、適切なタイミングで内服しないと思わぬ低血糖を起こすことや、せっかく内服したのにお薬の効果が得られないことがあるということです。ですから、指示されたタイミングで内服するようにしてください。
また、体調が悪いときや検査や手術の時にも飲み方に気をつけるお薬が。
 院長 藤田
院長 藤田ここでは、経口血糖降下薬の飲むタイミングと飲み忘れた時の対処の仕方、内服のタイミングで気をつける状況について解説いたします。
経口血糖降下薬の飲むタイミングについて
糖尿病のお薬にかかわらず、お薬は飲むタイミングが指定されています。
何となくいつ飲んだって変わらないのではというイメージもありますが、そのようなことはなく、それぞれ意味があります。
具体的には、「食前」「食直前」「食後」「食直後」「食間」「起床時」「時間指定」「頓服」「〇時間おき」など、さまざまなタイミングが。
経口血糖降下薬は特にタイミングがいくつもあって、複雑な面があります。また、例えば「食前」と「食直前」とはどう違うのか?など、言葉の定義が異なるものも。
少しでも理解しやすいように、まずは経口血糖降下薬でよく用いられる飲むタイミングの言葉の解説をして、具体的なお薬を提示いたします。
1)「食前」と「食直前」の違いについて
「食前」:食事の30分前の空腹時のタイミングです。ビグアナイド薬やSU薬があてはまります。これらのお薬では食後(食事後30分以内)でもかまいません。
「食直前」:食べる食前(どんなに遅くても内服後10分以内)のタイミングです。
αグルコシダーゼ阻害薬や速効型インスリン分泌促進薬があてはまります。速効型インスリン分泌促進薬を食事30分前に飲むと、食べる前に効果が発現して低血糖のおそれがあります。
2) 「朝食前」または「朝食後」に飲む薬
チアゾリジン薬やSGLT2阻害薬が、あてはまります。
※SGLT2阻害薬が朝に飲んだほうがいい理由として、夜に薬の濃度が高くなると夜中の頻尿の原因になってしまうからとされています。
3) 食事と関係なく内服していい飲み薬
DPP-4阻害薬があてはまります。
今回の経口血糖降下薬とは直接関係はありませんが、「食間」というタイミングもあります。食べている間という意味ではなく、食事と食事のあいだとのことで「食事を終えておおむね2時間後」という意味。
空腹で飲むと吸収の良い薬(漢方薬など)や、胃の粘膜を保護するためのお薬などに用いられるタイミングです。
内服を忘れてしまったらどうすればいいの?
処方されたお薬が「食前」と「食直前」のものであったりするとタイミングが複雑でつい飲み忘れてしまうこともありますよね。何となく飲み忘れに気がついた時に飲む、もしくは次の飲むタイミングでまとめて飲めばいいと思ってしまいがちです。
実際はまとめて飲むことは推奨されません。
 院長 藤田
院長 藤田飲み忘れに気がついたときに飲んだほうがいい薬と飲んではいけない薬があります。お薬の働き別に解説していきます。
インスリン抵抗性改善薬(インスリンの効きをよくする薬)
ビクアナイド薬:飲み忘れたことに気がついた時点で内服してかまいません。次の内服まで時間が短いときは内服しないでください。
チアゾリジン薬:朝食時に忘れた場合、昼食時に内服。それ以降であれば1回分の内服はとばしてください。
インスリン分泌を促進する薬
スルホニル尿素薬(SU薬):食後30分以内であればすぐに内服。それ以降のタイミングで飲み忘れに気がついた時は、そのタイミングの分はとばしてください。
速効型インスリン分泌促進薬: 食べ始めてから飲み忘れに気がついた時は内服しないでください。 低血糖を起こすことがあります。
DPP-4阻害薬
1日1回のお薬であれば、朝の飲み忘れに気がついたときはその時点で内服。気づいた時点で夕方の場合、内服はとばしてください。1日2回のお薬の場合は、午前中に朝の飲み忘れに気がついたときはその時点で内服。午後の場合は朝の分の内服はとばしてください。
αグルコシダーゼ阻害薬(糖の消化・吸収を抑え、食後高血糖を改善する薬)
食事の最中に気がついた場合のみ、すぐ内服してください。それ以降に内服しても効果はありません。
SGLT2阻害薬(尿と一緒に糖を排出させ、血糖値を下げる薬)
昼前に気がついた場合は内服してください。それ以降に気がついた場合は、その日の内服は中止。このお薬は尿の量を増やして尿へ糖分を排泄させる働きがあるので、午後以降に内服すると、夜中に尿量が増えてしまう恐れがあります。
ご飯を食べないときの飲み薬はどうしたらいいの?
食事による血糖上昇がないため、経口血糖降下薬はお薬の調整が必要となってきます。具体的な対応は、以下の通りとなります。
1) インスリン抵抗性改善薬(インスリンの効きをよくする薬)
ビクアナイド薬
1日1回の時:朝の分は昼、昼の分は夕に移動して内服。夕食を抜いた時は内服を中止。
1日2回の時:朝の分は昼に、夕食を抜いた場合は内服を中止。
1日3回の時:食べなかった食事の分は内服を中止。
チアゾリジン薬
1日1回であり、食事がとれた時に内服。
2) インスリン分泌を促進する薬
スルホニル尿素薬(SU薬)、速効型インスリン分泌促進薬
1日1回もしくは2回の時:朝分は昼に内服、夕食を食べない場合は夕分は内服中止。
1日3回の時:食べなかった食事の分は内服を中止。
3) DPP-4阻害薬
1日1回の時:朝の分は昼、昼の分は夕に移動して内服、夕食を抜いた時は内服を中止。
1日2回の時:朝の分は昼に、夕食を抜いた場合は内服を中止。
4) αグルコシダーゼ阻害薬(糖の消化・吸収を抑え、食後高血糖を改善する薬)
食事を抜いた時は内服を中止。
5) SGLT2阻害薬(尿と一緒に糖を排出させ、血糖値を下げる薬)
1日1回であり、食事がとれた時に内服。ただし、午後以降は内服を控えてください(夜中に尿量が増加してしまうためです)。
体調が悪いときでもお薬は飲んだほうがいいの?
体調が悪い時は血糖がいつもより変動しやすいため、注意が必要です 。
風邪や胃腸炎、発熱などで体調が悪い時(シックデイ=sick day:病気の日といいます。sickは病気の意味。)や、大きなケガや骨折をした時は、ストレスホルモンが出てインスリンの働きが低下し、血糖が高くなることがあります。
したがって、体調が悪い時は血糖がいつもより高くなりがちです。
一方、食欲が低下しいつもより食べる量が少なくなった時に、いつも通りの薬を内服すると思わぬ低血糖を引き起こすことがあります。このように、体調が悪い時は血糖がいつもより変動しやすいため、注意が必要です。
以下に簡潔にまとめますが、事前に体調不良になった時にどうするかを主治医の先生と相談しておくといいでしょう。
1) 内服を中止したほうがいい薬
ビグアナイド薬、αグルコシダーゼ阻害薬、チアゾリジン薬、SGLT2阻害薬
脱水で副作用が増強したり、胃腸炎症状が強くなることがあるので中止。
2) 状態によって調整したほうがいい薬
スルホニル尿素薬(SU薬)、速効型インスリン分泌促進薬
インスリンの分泌を増やすことによって血糖を下げるお薬です。よって、食事の量により量を調整する必要が。
体調が悪い時でも普段と同じかやや少ないくらいの食事量の場合は、いつも通りの量を内服してかまいません。
半分程度の食事量なら半分、半分以下の食事量なら内服を中止してください。実際食べてみないと食事量がわからないような時は、食直後に内服してもかまいません。
3) あまり気にしなくていい薬
DPP-4阻害薬
食事で上がった血糖に対して作用するので、食事をする場合は普段と同様に内服しても問題ありません。食べない時に飲んでもそれほど血糖低下作用はありません。
検査、手術の時のお薬はどうするの?
手術や造影剤の検査を行う際は事前に糖尿病の内服薬があることを伝えておくと、トラブルを防ぐことができます。
一般的に、手術の前は一時的に経口血糖降下薬を中止する必要があります。また、検査前の経口血糖降下薬で、一つ注意が必要な場面があります。
腎臓の機能が低下している方が造影剤を使用した検査を行う時には、ビグアナイド薬を飲んでいる場合は事前に中止しなくてはいけません。
ビグアナイド薬を内服中の患者さんヨード造影剤を使用して一時的に腎臓の機能が低下した場合、ビグアナイド薬の濃度が上昇し、乳酸アシドーシスを起こす危険性があるとされているからです。特に腎機能障害のある方がリスクとされています3) 。
糖尿病患者さんは、手術や造影剤の検査を行う際は事前に糖尿病の内服薬があることを伝えておくと、トラブルを防ぐことができます。
処方されたお薬は、患者さんそれぞれに合った薬の量と飲むタイミングが主治医から指示されているので、そのとおりに飲まないと十分な効果が得られなかったり、副作用のリスクが。
ご自身の判断で薬の量を調整することや、内服の中止は控えてください。もしわからないことや不安なことがあれば、遠慮なく主治医や薬剤師に相談しましょう。
症状がないのになぜ血糖を下げなければいけないのか?
糖尿病には、神経障害、網膜症、腎症、脳梗塞や心筋梗塞などさまざまな合併症が あります。
糖尿病は、「高血糖が慢性的に持続する」病気です。糖尿病と診断された方は、高血糖を改善する、つまり血糖を下げる治療を行っていく必要があります。
高血糖の時に喉が渇いたり、おしっこの尿が増えたり、疲れやすくなる、体重が減るなどの症状がでることがありますが、多くの場合は、自覚症状がありません。
自覚症状がないまま糖尿病と診断された場合、「なぜ症状も特になくて体調もいつも変わりないのに治療しなくてはいけないのだろう?」「治療してもしなくても変わりないだろうから面倒くさいし、副作用があったらいやだから治療したくないな…」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
実際、糖尿病の患者さんにおいて、医療機関受診を途中で中止してしまったり、治療をきちんと行えていない方が相当数いらっしゃいます。
しかし、症状がないからといって、高血糖を放置しておくことは非常に危険なことです。高血糖の状態が続いてしまうと、血管やいろいろな臓器にダメージを与えてしまいます。
その結果、神経障害、網膜症、腎症、脳梗塞や心筋梗塞などさまざまな合併症が。
いずれの合併症も生命の危機を脅かし、生活の質を著しく低下させてしまいます。
治療の目的は血糖を下げて、高血糖状態を改善することで合併症を発症しない、発症している方はこれ以上合併症を進行させないことです。
治療は糖尿病と診断したら早期に開始し、継続していくことが重要です。日本糖尿病学会のガイドラインでは、治療時期について次のように記載されています。
「血糖コントロールの目標は、可能な限り正常な代謝状態を目指すべきであり、治療開始後早期に良好な血糖コントロールを達成し、その状態を維持することができれば、長期予後の改善が期待できる」4)。
血糖の目標値はどれくらいなのですか?
目標値としてHbA1cを7.0%未満、 空腹時血糖を130mg/dL未満、食後2時間血糖値を180mg/dL未満がおおよその目安。
糖尿病患者さんの治療の目標は、合併症を発症しない、合併症を発症した場合もこれ以上進行させないこととお伝えしました。では、具体的にどのような管理をすれば目標を達成できるのでしょうか。
日本糖尿病学会で血糖コントロール目標を以下のように定めています。
この表で注目する点は、合併症予防のための目標値としてHbA1cを7.0%未満にする、とあることです
血糖を測定している方は、空腹時血糖を130mg/dL未満、食後2時間血糖値を180mg/dL未満をおおよその目安としましょう。
ここで、HbA1cという言葉がでてきました。糖尿病患者さんでは定期的に外来フォローされる際に血液検査で測定される項目の一つですが、重要なので、ここで少し解説。
HbA1cは、ヘモグロビンエーワンシーと読みます。ヘモグロビン(Hb)は、ヒトの血液成分の一つで主な働きとして全身に酸素を運ぶ役割が。ヘモグロビンのなかでブドウ糖とくっついたものをHbA1cといいます。
~イメージ~
ヘモグロビンとブドウ糖がいったんくっつくと、しばらくはくっついたまま離れません。高血糖、つまり血液の中のブドウ糖が多いと、ブドウ糖とくっつくヘモグロビンの割合がどんどん増えていきます。よって、HbA1cが高い=血糖が高い状態が続いているということに。
どれくらいの期間を反映するかといいますと、HbA1cは過去1-2か月間の平均血糖状態を反映するとされています。HbA1cは平均血糖を表すため、採血の日の食事の影響を受けません。
HbA1cは平均血糖状態を表す指標で、この数値を安定して保つことが合併症を起こさないうえで大切です。この目標を達成するために薬物療法などの治療を調整していきます。
低血糖になった時の対応はどうすればいいの?
 院長 藤田
院長 藤田薬物療法の中で、一部の飲み薬(SU薬や速効型インスリン分泌促進薬)やインスリン注射を使用した場合、効果が強くあらわれて時に低血糖を起こすことがあります。
なお、低血糖は、血糖値で70mg/dL未満という定義もありますが、あくまで目安であり、以下にあげる症状があるかなど総合的に判断してください。
脳はブドウ糖のみをエネルギー源としているために、低血糖では脳のエネルギー不足を引き起こしてしまいます。
低血糖は適切に対処しないと重篤な事態が起こることもあるので注意が必要です。
低血糖が起こりやすい状況と症状
<低血糖が起こりやすい状況>
- お薬の量が多い時
- 食事量が少ないもしくは食べなかった、食事の時間が遅れてしまった時
- お酒を飲み過ぎた時
- いつもより運動の量が多かったり、運動時間が長かったりする時
<低血糖の症状(下にいくほど重篤な症状)>
- 強い空腹を感じる(食べてからそんなに時間がたっていないのにやたらおなかがすく)
- 冷や汗をかく、手指のふるえ、動悸、不安感
- 眠気、強い脱力感、めまい、集中力の低下
- 痙攣、意識消失、昏睡
糖尿病患者さんで先に挙げた治療を行っている方で、(低血糖を起こしうる状況では特に)低血糖症状に当てはまる症状があった場合は、速やかに対処するようにしましょう。
低血糖の対処方法と注意点
<低血糖の対処方法>
- ブドウ糖10gを摂取
- 糖分を含むジュースを150-200ml摂取
1)、2)のいずれかの対応をして15分たっても改善しなければ再度同じ対応をしてください。
<低血糖対応時の注意点>
- 飴は吸収がゆっくりのため低血糖時には適しません。
- 人工甘味料は血糖をあげる働きがないので、低血糖時には使用しないでください
- α-グルコシダーゼ阻害剤を飲んでいる人は、砂糖が吸収しにくい状態になっているので必ずブドウ糖をとるようにしましょう。
また、自動車を運転しているときに低血糖がおこると重大な事故につながりかねません。低血糖になる可能性の患者さんは、運転前に血糖値を確認したり、低血糖時に対応ができるようにブドウ糖などをあらかじめ準備しておきましょう。
もし運転中に低血糖かもしれないと感じたら、あわてずに車を安全な場所に停車させて速やかな対処をするようにしてください。
糖尿病の薬物治療を受けている場合、市販薬で気をつける薬はあるの?
糖尿病患者さんが市販薬を使用する際に注意すべき点があります。
具体的には、
①糖尿病のお薬と相互作用がないか
②市販薬の中に血糖をあげるものがある
という2点です。
糖尿病のお薬と相互作用
 院長 藤田
院長 藤田薬の組み合わせのことを薬物相互作用といいます。相互作用により、薬物の効果が増強したり、減弱したりします。糖尿病のお薬に相互作用を有するものを紹介します。
1) 解熱鎮痛薬(アスピリン)
アスピリンは解熱鎮痛薬として使用されることも多いお薬です。このお薬は大量に内服すると血糖降下作用があります。
アスピリンが糖尿病のお薬の作用を増強するからです。
2) 消化酵素薬(ジアスターゼ)
総合胃腸薬などに含まれているジアスターゼは、αアミラーゼ活性というものがあります。
糖尿病薬の一つであるαグルコシダーゼ阻害薬は、αアミラーゼ活性を阻害する働きが。
このため、ジアスターゼを内服するとαグルコシダーゼ阻害薬の効果を打ち消してしまうおそれがあります。
3) 健康食品
グァバ葉やコーヒー、赤ワインなどに含まれるポリフェノールや大豆(黒豆)を発酵させて作られた豆鼓(とうち)は、αグルコシダーゼ阻害薬と同じような働きがあります。
そのため、αグルコシダーゼ阻害薬を内服している患者さんは、これらの食品をとると薬の効用が増大するおそれが。
市販薬で血糖をあげるもの
代表的なものは、プソイドエフェドリンです。これはアドレナリン作動薬といって交感神経を刺激して血糖を上昇させる作用が。
これらは、鼻炎薬や風邪薬に多く含まれています。
また、咳止め薬などに含まれるメチルエフェドリン塩酸塩、漢方薬の成分にある麻黄(葛根湯など)も同じような理由で血糖を上昇。
これらの成分はドラッグストアに売っている風邪薬に多く含まれています。
市販薬を購入する際は、これらの成分が極力含まれていない成分のお薬が良いでしょう。ドラッグストアで相談してみてください。
お薬を忘れないためのちょっとしたコツは?
経口血糖降下薬はたくさんの種類があり、飲むタイミングもさまざまで、内服するだけでも非常に大変です。
なるべく飲み忘れを少なくするために、ちょっとした工夫について紹介いたします。
①あらかじめ1回に飲むお薬を整理しておきましょう
お薬の種類が多いと飲む度に薬の準備をするのは大変ですよね。薬の種類が多い場合には、1回に飲む薬をあらかじめ整理しておくと間違いが減るかと思います。事前に整理しておきましょう。
ピルケースや服薬カレンダーなどを利用してみてはいかがでしょうか。
②1包化に調剤してもらう
糖尿病患者さんは複数の経口血糖降下薬を内服することがあります。それに加えて他の病気をお持ちの場合は、さらにお薬が増えてしまい、間違いが起こりやすく。
処方されたお薬をまとめて1つの袋に入れてもらう「一包化」をしてもらうこともできます。
③配合薬を処方してもらう
経口血糖降下薬の中には1剤の中に2種類以上の成分を含んだ「配合薬」があります。配合薬を選ぶことで錠数を減らせる場合があります。
④飲むタイミングを調節してもらう
お薬を飲むタイミングが多いと、飲み忘れや飲み間違いのおそれがあります。また、自分の生活スタイルに内服タイミングが合わせにくいこともあるかもしれません。
ご自身が最も飲み忘れしにくい時間帯に内服のタイミングをそろえてもらうことが可能か、病院や薬局で相談してみるのも一つの手です。
具体的な例として、食前と食後に飲むように指示されているお薬をまとめて食前にすることが可能かどうか、相談してみるのもいいかもしれません。
普段のお薬を把握してもらい、気軽に相談にのってもらえるかかりつけの薬局さんを作ってみるのもいいでしょう。
まとめ
経口血糖降下薬は種類が多く、それぞれどのように糖尿病に効くのか異なるので、患者さんは処方されたお薬の指示された量・タイミングを守る必要が。
ご自身に処方されたお薬がどのような特徴かを把握することで、副作用や気を付ける点を理解し、内服する意味がわかればより治療継続しやすくなるかと思います。
血糖コントロールにお悩みの方が食事療法、運動療法を続けながら薬物療法を併用することで高血糖を改善し、健康な人と変わらない寿命、生活の質を維持する人生を送ることができるよう、少しでも助けになれば幸いです。
この記事を書いた人

内科総合クリニック人形町 院長
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医
東京大学医学部保健学科および横浜市立大学医学部を卒業
東京大学付属病院や虎の門病院等を経て2019年11月に当院を開業
最寄駅:東京地下鉄 人形町駅および水天宮前駅(各徒歩3分)
参考文献
- 糖尿病治療ガイド2018-2019. 文光堂. 2018年.
- 日本糖尿病学会:SGLT2阻害薬の適正使用に関する Recommendation http://www.fa.kyorin.co.jp/jds/uploads/recommendation_SGLT2.pdf
- 日本糖尿病学会:メトホルミンの適正使用に関するRecommendation http://www.fa.kyorin.co.jp/jds/uploads/recommendation_metformin.pdf
- 糖尿病診療ガイドライン2019. 南江堂 2019年.