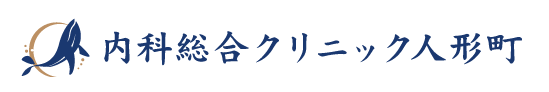糖尿病は、血糖が高い(高血糖)状態が続く病気で、血糖を下げて高血糖状態を改善することが必要です。治療方法には食事療法、運動療法、薬物療法の3つがあります。
糖尿病の治療と聞くと、インスリンなどの薬物療法を想像される方が多いのではないでしょうか?実際は、食事療法と運動療法が糖尿病治療の基本で、最初に行われます。
とりわけ、食事療法は糖尿病の患者さんすべての方に必要な治療法です。
この記事の執筆者

藤田 英理 内科総合クリニック人形町 院長
東京大学医学部保健学科、横浜市立大学医学部を卒業。虎の門病院、稲城市立病院、JCHO東京高輪病院への勤務を経て内科総合クリニック人形町を開院。総合内科専門医。AGA治療や生活習慣病指導も行う。
食事療法の重要性
食事療法と言うと、「食べたいものが食べられず、つらそう」「薄味でおいしくないものを少ししか食べられず、つまらない」「食事が楽しめないなら、自分は好きなものを食べて、太く短く生きる!」などという患者さんの声をよく聞きます。
糖尿病の食事療法と聞くと、カロリーや食べ物の種類を厳しく制限しなくてはならず、甘いものは御法度で、大変という印象を持たれている方も多いと思いでしょう。
 院長 藤田
院長 藤田実際は、とても厳しい制限が必要なものではなく、絶対に食べてはいけないものはありません。食事療法は、適切なエネルギー量でバランスのよい食事を規則正しく食べることが大切です。
2型糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンの量が低下(インスリン分泌能低下)したり、インスリンの効き目が不十分(インスリン抵抗性の増大)になることで高血糖を発症します。
高血糖は、生活習慣と大きな関わりがあり、食事バランスや運動不足などが大きく影響。食事療法をすることで、体重が減少し、インスリンの効き目がよくなり、血糖値の改善に大きく寄与します。
糖尿病の食事療法の進め方
糖尿病患者さんは、食事療法を行うにあたり、まず病院で栄養指導が行われます。栄養指導の場で具体的にどのようなことを指導されるかというと、昔は一様にカロリーの計算や食習慣の改善を指導するというものがほとんどでした。
しかし、現在は患者さん一人ひとりの生活に合わせて、無理のない方法を見い出し、実現できるようにするのが基本です。
日本糖尿病学会の一番新しいガイドラインには、糖尿病における食事療法は総エネルギー量や栄養素の摂取比率は患者さんの状態に応じて柔軟に対応すると記述が。1)
ここでは、病院で指導されることの多い内容について解説します。
栄養指導の大まかな流れは以下の通りです。
①:普段の食生活をはじめとした生活習慣についての聴取
↓
②:聴取した内容や検査結果を元に、食生活の問題点がないか検討
↓
③:目標体重や普段の活動度よりエネルギー摂取量を決定
↓
④:エネルギー摂取量に応じて栄養素の配分
↓
⑤:③、④で決めたエネルギー摂取量や栄養素に基づいて自宅でどのような食品を選択するべきか指導
↓
⑥:食事療法が実践できているか定期的に評価、修正点がないか確認
ここで、栄養指導のはじめの一歩である普段の生活習慣についてどのようなことを聞かれるかについて解説していきましょう。
*エネルギー摂取量や、どのような栄養素をとればいいのかについては後ほど解説。

- 食事の回数やタイミング
食事は1日何回ですか?
朝食、昼食、夕食は何時頃食べますか?
1回の食事時間はどれくらいですか?
- 食事内容について
主食(ご飯、パン、麺)はどれくらい食べますか?(例:ごはんは茶碗1杯なのか大盛りにしたり、おかわりすることが多いかなど)
肉、魚、卵、乳製品、果物、野菜はどれくらい食べますか?
- 飲み物について
ジュース、糖分が入ったコーヒー、紅茶などはどれくらい飲みますか?
- 嗜好品について
アルコールは飲みますか?飲むとしたらどれくらいですか?
間食はしますか?
たばこは吸いますか?
- 普段の食事場所について
自炊もしくは家族の方が食事を用意してくれますか?
外食は週何回しますか?
- 運動習慣について
普段運動する習慣はありますか?
- 睡眠時間について
何時に起床/就寝しますか?
- 仕事内容について
お仕事は何をされていますか?
仕事は不規則ですか?(例:シフト制、夜勤があるかなど)
食事療法でまず大切なことは、普段の生活習慣に問題点がないか確認し、修正すべき点があれば改善することです。
上に挙げた内容を医療者に伝えるのはとても大変なことだと思いますが、栄養指導をよりよいものにするためにできる範囲で伝えるといいでしょう。
伝えやすくするために、栄養指導を受ける前に記録を残しておくことをおすすめします。食べたものや食べた量、食べた時間をメモしておく、もしくは食事内容を携帯電話のカメラで撮影してみてはいかがでしょうか。
また、平日だけでなく、休日の記録も残しておくといいでしょう。毎日の記録は大変なので、まずは数日~1週間の記録をしてみましょう。
普段の生活習慣を聴取した内容などを元に、目標体重やエネルギー摂取量を設定します。設定されたエネルギー量を摂取するにあたり、患者さんそれぞれの生活に合わせた食事がとれるよう指導。
具体的には、食事を楽しめるような工夫、負担の少ない調理法、摂取したほうがいい食材、控えたほうがいい食材、使い勝手のいい便利な食材、糖尿病でない方との食事の際のポイント、食べる順番、外食や会食時における注意点などを指導されます。
さらに、食事療法において理解していただきたい大切なポイントは以下の通りです2) 。
- 腹八分目とする
- 食品の種類はできるだけ多くする
- 動物性脂質(飽和脂肪酸)は控えめに
※飽和脂肪酸:肉類や乳製品の脂肪に多く含まれており、コレステロール値を上げ、中性脂肪を増やすと言われています。
- 食物繊維を多く含む食品(野菜、海藻、きのこなど)を摂る
- 朝食、昼食、夕食を規則正しく
- ゆっくりよくかんで食べる
- 単純糖質を多く含む食品の間食を避ける
※単純糖質:砂糖や果物、菓子類に含まれるブドウ糖、果糖、ショ糖を指し、血糖を急上昇させます。
効果を知ってモチベーションをアップ~食事療法の有効性~
食事療法は糖尿病治療の基本であり、患者さんすべてに必要な治療法である、とお話しましたが、実際に食事療法はどのような効果が見込まれるのでしょうか。
 院長 藤田
院長 藤田食事療法が糖尿病の患者さんにもたらす具体的な効果について、解説していきます。
糖尿病合併症の抑制
2006年-2016年に日本人の2型糖尿病患者さんを対象として糖尿病合併症を抑制するための介入試験(J-DOIT3試験)が行われました。従来の糖尿病治療をした人と比べて、管理栄養士によるよりきめ細かな食事療法の強化治療をした人のほうが、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病性腎症の発症・増悪、糖尿病性網膜症などの合併症が少ないという結果に3) 。
血糖コントロールの改善
肥満を伴う2型糖尿病患者さんに対して食事療法と運動療法を積極的に行う人と、そうでない人に分けて研究したところ、積極的な治療を行った人達においてHbA1c (ヘモグロビンエーワンシー) の低下がみられました4) 。

血液成分の一つであるヘモグロビンにブドウ糖がくっついたもので、過去1-2か月間の平均血糖を反映する、血糖コントロールの重要な指標で、HbA1cを安定させることが合併症を起こさないために大切です。
また、食事の際に野菜から食べると、食後の高血糖が改善し、血糖の変動が抑えられることが認められました5) 。
その他にも、食事の炭水化物量を調節するカーボカウントと呼ばれる食事療法があります。主にインスリン治療が必要な1型糖尿病患者さんで普及していましたが、2型糖尿病患者さんでも血糖コントロールの改善が期待されています6) 。
心臓血管疾患のリスク因子の改善、体重減少
2型糖尿病の患者さんに行われたいくつかの研究をまとめて解析した報告によると、食事療法を中心とした生活習慣の介入を行うことによって、これまでに知られている心臓血管疾患のリスク因子の数値が改善することが認められました7, 8) 。
具体的には、LDLコレステロール値の低下、HDLコレステロール値の上昇、中性脂肪の低下、血圧の低下です。
LDLコレステロールは肝臓で作られたコレステロールを全身へ運ぶ働きがありますが、増えすぎると動脈硬化を起こし、心筋梗塞や脳梗塞を発症させるリスクが高くなり、悪玉コレステロールとも呼ばれています。
HDLコレステロールは血液の余分なコレステロールを肝臓に運ぶ働きをしており、動脈硬化を抑える働きが。善玉コレステロールとも呼ばれています。
また、体重減少の効果も認められました。体重が減ると自身の分泌するインスリンの効きがよくなる(インスリン抵抗性が改善する)ことで血糖コントロールが改善します。
心臓血管疾患のリスク因子の改善、体重減少
2型糖尿病の患者さんに行われたいくつかの研究をまとめて解析した報告によると、食事療法を中心とした生活習慣の介入を行うことによって、これまでに知られている心臓血管疾患のリスク因子の数値が改善することが認められました7, 8) 。
具体的には、LDLコレステロール値の低下、HDLコレステロール値の上昇、中性脂肪の低下、血圧の低下です。
LDLコレステロール( 悪玉コレステロール )は肝臓で作られたコレステロールを全身へ運ぶ働きがありますが、増えすぎると動脈硬化を起こし、心筋梗塞や脳梗塞を発症させるリスクが高くなります。
HDLコレステロール(善玉コレステロール)は血液の余分なコレステロールを肝臓に運び、動脈硬化を抑える働きが。
また、体重減少の効果も認められました。体重が減ると自身の分泌するインスリンの効きがよくなる(インスリン抵抗性が改善する)ことで血糖コントロールが改善します。
実際どのくらい食べてもいいの?
総エネルギー摂取量(カロリー)=目標体重×エネルギー係数
糖尿病の患者さんに限らず、摂取するエネルギーが消費するエネルギーよりも過剰になると体重が増え、肥満につながります。
糖尿病の患者さんにおいて、肥満はインスリンの効きを低下させ、高血糖状態が持続し、血糖コントロールが困難になる危険性が。エネルギー摂取が過剰になり、太ってしまわないように配慮する必要があります。
一方、エネルギー制限が必要だからといって、極端にエネルギー制限をすることは必要な栄養素が足りなくなったり、筋肉量が低下し、かえって健康を害してしまうことも
それでは、摂取すべきエネルギー量はどのように決めればいいのでしょうか。
 院長 藤田
院長 藤田人によって適切なエネルギー摂取量は異なり、性別、年齢、肥満の度合い、普段の身体活動量、合併症の有無などを考慮してエネルギー摂取量は設定されます。
具体的にどのようにエネルギー摂取量を求めていくか、そしてエネルギー摂取量を決める上で必要な目標体重の設定の目安について解説していきます。
1日あたりの総エネルギー摂取量の目安は以下の計算式によって算出。
総エネルギー摂取量(カロリー)=目標体重×エネルギー係数
計算式にあるように、エネルギー摂取量を決めるためには目標体重とエネルギー係数が必要です。それぞれどのように設定していくのかみていきましょう。
<目標体重>
年齢によって以下のように算出。
- 65歳未満:[身長 (m)] × [身長 (m)] × 22
- 65-74歳 :[身長 (m)] × [身長 (m)] × 22-25
- 75歳以上:[身長 (m)] × [身長 (m)] × 22-25 (状態により適宜判断)
計算式にある22-25の数字はBMI (Body mass indexの頭文字をとったもの)です。BMIは肥満度を表す指標として国際的に用いられている体格指数で、25以上が肥満とされています。
<エネルギー係数>
エネルギー係数とは、普段の身体活動量と病態に基づいたエネルギー必要量のことです。以下の目安を参照して柔軟に設定することが望ましいとされています。
- 軽い労作(デスクワークが多い、1日の大部分が座って過ごす、運動習慣がないなど):25-30
- 普通の労作(座っていることが多いが、通勤・家事、軽い運動習慣があるなど) :30-35
- 重い労作(力仕事、普段から活発な運動習慣がある) :35~
目標体重とエネルギー係数を決めてエネルギー摂取量を計算してみましょう。
例:身長 165cmでデスクワークが多く、普段運動習慣がない人の場合
目標体重:1.65(m)×1.65(m)×22=59.8(kg)
エネルギー係数:軽い労作に該当するため係数は25 -30
総エネルギー摂取量(カロリー)=目標体重×エネルギー係数なので
この方のエネルギー摂取量は59.8(kg)×25 – 30=1495 ~ 1794 カロリーとなります。
ただし、肥満の方にこの計算式をあてはめると目標体重に到達するには大幅な減量が必要となります。
例えば身長165cm、体重80kgの方の場合、目標体重は59.8kgなので20kgの体重減少が必要に。いきなり20kgの減量というのは非常に困難を伴いますし、極端な食事療法は健康を害する恐れがあります。肥満の方は、いきなり目標体重を目指すのではなく、まず3%の体重減少を目指すようにしましょう。
食べていいもの、悪いもの
糖尿病になったからといって食べてはいけないものはありませんが、食べ過ぎないように気を付けるべきもの、食べる量を考ること、食べるタイミングや食事時間、順番も大切 です。
糖尿病になった方が、病院で食事療法をしましょう、といわれた時によくイメージされるのが「甘いものはもう食べてはいけない、これから厳しい食生活をずっとしなくてはいけないのか」、ということです。
実は、糖尿病になったからといって食べてはいけないものはありません。大切なことは、食べるものや食べる量を考えることです。また、食べる量や食べるものだけでなく、食べるタイミングや食事時間、食べる順番も大切です。
糖尿病の患者さんが食べる量に気をつける食べ物や、逆に摂取したほうがいい食べ物、気をつけたい食事習慣について解説する前に、食べ物がどのように血糖に影響するのかを書いてみます。
3大栄養素
食べ物の中で、人の身体になくてはならない栄養素のうち、エネルギー(カロリー)源となる3つの栄養素を「3大栄養素」といいます。3大栄養素は炭水化物、たんぱく質、脂質です。それぞれの大まかな働きは以下となります。
1)炭水化物
腸から吸収されて、主に脳や筋肉などの細胞が活動するためのエネルギー源となります。
2)たんぱく質
筋肉や臓器などのからだを構成する要素の材料となる重要な栄養素です。
3)脂質
からだのエネルギー源となり、ホルモン、細胞などを作る材料となります。
三大栄養素
3大栄養素と血糖の関係
3大栄養素はどのように血糖値へ影響を及ぼすのか、まず下図をご覧ください。
食事した直後から血糖が急激に上昇し、食後30分-1時間にかけてピークになるのが炭水化物です。
その後、食後数時間かけて高くなるのがたんぱく質。最後に、食後6~12時間かけてゆっくりと上昇するのが脂質です。
炭水化物はたんぱく質や脂質と異なり、ほぼ100%がブドウ糖に変換され、かつ急激に血糖を上げるため、血糖値に大きく影響します。
気をつける食べ物:糖質
 院長 藤田
院長 藤田糖尿病の患者さんで絶対食べてはいけないものはありません。しかし、食べ過ぎないように気をつけたほうがいい食べ物は糖質。糖質は炭水化物の一部です。
糖質=砂糖などの甘いものというイメージがあるかもしれませんが、ごはん、とうもろこしなどに含まれるでんぷんも糖質の一部ですし、甘く感じないものも実は糖質が多く含まれています。
糖質に関する言葉はたくさんあります。炭水化物をはじめとして、糖質、食物繊維、糖類(ブドウ糖、でんぷん、果糖、単糖類、二糖類、多糖類)などが挙げられます。
糖質を考慮するうえで、「炭水化物、糖質、食物繊維、糖類、多糖類」の違いについて理解しておくと、栄養指導を受ける際や、他の書物などの媒体をみる際に、混乱することがありません。
炭水化物、糖質、食物繊維、糖類の違いは以下のようになります。
炭水化物とは糖類、糖質、食物繊維の総称です。
炭水化物=糖質+食物繊維
次に糖質とは糖類、多糖類、糖アルコールの総称です。
糖質=糖類+多糖類+糖アルコール
最後に糖類は単糖類と二糖類の総称です。
糖類=単糖類+二糖類
言葉だけでまとめると少しわかりにくいので、以下の図をご覧いただくと、分かりやすいと思います。
単糖類、二糖類、多糖類、糖アルコールにはどのような食べ物が該当するのか、そして食物繊維についてのお話をしていきます。
単糖類
糖質の中でも一番小さいのが単糖類。単糖類は以下のものがあります。
- ブドウ糖(別名:グルコース)
ブドウ糖は自然界に最も多く存在する単糖類で、筋肉や血液、内臓を働かすためのエネルギー源となります。食べ物から摂取された糖質は、消化吸収を通してブドウ糖に分解されることではじめてエネルギーとして利用できます。
- 果糖(別名:フルクトース)
果物、はちみつなどの食品に含まれて、コーラやジュースなどの清涼飲料水や菓子類などの加工食品にも含まれています。
- ガラクトース
乳糖の成分となります。
二糖類
単糖類が2個くっついたものが二糖類。どの単糖類がくっついているかで名前が異なり、二糖類は以下のものがあります。
麦芽糖(マルトース)= ブドウ糖 + ブドウ糖 例) 水飴、甘酒など
ショ糖(スクロース) = ブドウ糖 + 果糖 例) 砂糖など
乳糖(ラクトース) = ブドウ糖 + ガラクトース 例) 牛乳など
※単糖類と二糖類は大きさが小さく消化吸収も早いので糖質の中でも血糖を急激に上昇させます。
多糖類
多くのブドウ糖がくっついてできる糖類を多糖類といいます。多糖類は糖質なので血糖をあげますが、単糖類や二糖類と比べて分解されてブドウ糖になるまでに時間がかかる、つまり血糖の上昇は比較的緩やかなので食事の炭水化物は多糖類を中心にするといいでしょう。
多糖類の代表的なものはお米、パン、小麦粉、いも類などに含まれるでんぷんです。
糖アルコール
砂糖に比べ甘味は低いですが、吸収されにくいため血糖への影響はほとんどないとされています。 甘味料として使用され、虫歯の原因となる酸を作らないため虫歯予防の食品などに使用。一度に多量に摂取するとおなかが緩くなることが。
ソルビトール、エリスリトール、マルチトール、キシリトールなどがあります。
食物繊維
食物繊維は人の消化酵素で消化されない食物中の難消化性成分のことをいい、いわゆる私たちがイメージする炭水化物とは少し性格が異なります。
糖質はエネルギー源となりますが、食物繊維は消化されずエネルギー源とはなりません。よって糖質とは異なり、食物繊維は血糖を上げません。食物繊維は大きくわけて不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の2つに分けられます。
不溶性食物繊維:水に溶けにくい食物繊維のことで、きのこやごぼう、野菜やくだもの、豆類などの食品や、穀物の皮(小麦ふすまなど)に多く含まれ、胃や腸で水分を吸収してふくらみ、腸を刺激して便通を促します。噛みごたえのあるものが多く、満腹感が得やすいです。
水溶性食物繊維:水に溶けやすい食物繊維のことで、オクラや昆布などのネバネバとした粘着性のある食品や、くだもの、こんにゃくなどに含まれます。糖質の吸収がゆっくりになり、食後の血糖の急な上昇を抑える働きが。
食物繊維は糖尿病の患者さんにとってメリットのある食べ物であり、日本糖尿病学会のガイドラインでも1日20g以上の食物繊維を摂取することが推奨されています1) 。
最近食品以外にも、トウモロコシデンプンから作られた難消化デキストリンが使われるようになりました。特定保健用食品(いわゆるトクホ)として認可されており、食後の血糖上昇を抑える働きがあります。
積極的にとりたい食べ物:海藻類、野菜、果物
その他に糖尿病の患者さんにおいて摂取してもらいたい物は、ビタミンやミネラルを含んだ食品です。海藻類、野菜、果物に多く含まれています。
ビタミンやミネラルそのものは、血糖に対する効果が明らかではありませんが、カルシウムは骨や歯の材料となり、鉄や亜鉛などのミネラルやビタミンは、体の働きを正常に保つために必要です。
糖質の多い野菜
ここで一つ注意点があります。
野菜はミネラル、ビタミンを含んでいて積極的に摂取したい食べ物ではありますが、一部の野菜は糖質を多く含んでいるため食べすぎると血糖が上昇してしまい、注意が必要です。
特にいも類は糖質が多く含まれているので、摂りすぎに注意しましょう。
1) いも類
さつまいも、じゃがいも、さといもなど
2) 根菜類
ごぼう、れんこん、にんじんなど
3) その他
かぼちゃ、とうもろこし、たまねぎなど
食べる順番・食事量
注意するべき食べ物と積極的に撮るべき食べ物のほかに、食べる順番や食事量も大切です。
食べる順番
食べる順番療法のポイントは、食物繊維の多く含まれる野菜類を先に食べ、次にたんぱく質(肉、魚)のおかずを食べ、炭水化物を最後に食べることです。そして食べる時はゆっくりよく噛んで食べることが重要。
みなさんは「ベジファースト」という言葉を聞いたことはありますか?野菜からはじめに食べましょうという食事方法でダイエット法として紹介されることも。
「食べる順番療法」は野菜から先に食べることで糖質の吸収を遅らせ、食後の血糖上昇を抑え、体重減少が期待できます9) 。
野菜に含まれる食物繊維が糖質の消化吸収を遅らせ、おかずのたんぱく質などが小腸からGLP-1(インスリン分泌を促すホルモン)を分泌することで、血糖上昇が抑制。
にぎりこぶし1個か2個分の野菜を5分以上かけて食べ、その後、肉・魚・卵・大豆などのたんぱく質のおかずを5分以上。最後に、炭水化物であるごはん、麺類、パン、いも類を残りのおかずと一緒に5分かけて食べます。野菜類を食べ始めてから、炭水化物を食べるまでに10分以上の時間差があることが必要です。
食べる順番を変えることは食事内容を変えずに、血糖上昇の抑制や体重減少が期待できるストレスの少ないやり方ですので、ぜひ試してみてください。
食事量の配分
栄養指導で1日のエネルギー摂取量の目安を指導されることが多いのですが、これだけ聞くと、1日の目安量を超えなければ1食だけたくさん飲み食いしていいように思うかもしれません。
しかし、食事量のばらつきが生じると(特に糖質を多くとりすぎた場合)、食後の血糖が著明に上昇するなど、血糖のばらつきが生じ、薬物療法を行っている方は低血糖になりかねません。
一方、糖尿病の患者さんが食べ放題に行ってはいけないということはありません。食べ放題は、ご自身で料理を選び、量も調節することが可能ですので、十分に楽しむことができます。
大切なことは、適正なエネルギー量の中で栄養素だけでなく、量のバランスにも気をつけて食べることで、ストレスの少ない食事をしていただくことです。
血糖の目標値
糖尿病の治療目的は、血糖を下げて、高血糖状態を改善することで合併症を発症しない、発症している方はこれ以上合併症を進行させないこと。
そして健康な人と変わらない寿命、生活の質を維持することで「健康な人と変わらない人生」を送ることです。
では、具体的にどのような目標値があるのでしょうか。日本糖尿病学会の血糖コントロール目標をご紹介します。
図 血糖コントロール目標1)
糖尿病の合併症を予防するための目標は、HbA1c7.0%未満にすることです。この血糖コントロールは成人の目標であり、小児の方や妊婦の方にはあてはまらないので注意してください。
また、高齢者の方はこの基準とは異なった目標が設定され、治療内容、認知機能、可能な日常生活動作によって目標が異なります。
ポイントは、低血糖を極力起こさないようにするため、成人のように厳密に管理しすぎないということです。
図 高齢者における血糖コントロール目標(HbA1c値)10)
糖質制限はしてもいいですか?
糖質制限は、肥満や血糖コントロールの改善を目的に食事の中の糖質を減らし、糖質制限で不足するエネルギーをたんぱく質や脂質で補う食事療法の一つです。
糖質制限に厳密な定義はなく、制限する糖質の量も1日70-130g、1日100g以下、1日の総エネルギー量の40%などいろいろな報告が。
糖質制限は、食事にともなう血糖上昇を抑えることで過剰なインスリン分泌を回避することが期待されます。
また、たんぱく質と脂質の摂取は食欲を抑制する働きもあり、摂取エネルギー量が減少することもあり、糖尿病の患者さんにおいて糖質制限は食後高血糖を改善し、減量の効果も期待されています。
しかし、糖質制限には注意点がいくつか存在します。
- 低血糖を起こす場合ことも
スルホニル尿素薬やインスリン注射をしている患者さんは薬の調整が必要。 - たんぱく質や脂質の過剰摂取
糖尿病性腎症や動脈硬化のリスクを高める可能性。 - 塩分過剰になりやすい
糖質制限では副食中心になるため、これまでの味付けでは食塩過剰になる可能性が。 - 高齢者では筋肉量が低下するおそれ
糖質制限でエネルギーが不足してしまうと、体は筋肉を分解してエネルギーを作ろうとし、その結果筋肉量が低下するおそれが。高齢者では特に注意が必要。
糖質制限は人によっては効果がある方もいらっしゃいますし、有効とする研究報告もでてきています。しかし、有効でないとする研究報告も存在し、糖質制限の是非については未だ議論がつづいているところです。
 院長 藤田
院長 藤田炭水化物量をやや少なめにする(例えば総エネルギー摂取量の50%くらいにする)などの柔軟な対応をすることは問題ないでしょう。
人工甘味料は摂取してもいいですか?
人工甘味料は、人工的に化学合成によって作られた甘味料のことです。代表的なものにアスパルテーム、アセスルファムカリウム、スクラロースなどがあります。
人工甘味料のカロリーは、アスパルテームは1gで4カロリーと砂糖と同じ。アセスルファムカリウム、スクラロースはともに0カロリーです。
これらの人工甘味料は、砂糖の数百倍の甘味度があり、砂糖と比べて極めて少量で甘みを実現することができるため、ダイエット飲料やお菓子に利用されています。
糖類は強く血糖上昇をさせますが、人工甘味料はどうでしょうか。人工甘味料にはブドウ糖が含まれないため、基本的に血糖は上昇しません。
糖類と違って血糖も上昇させず、甘みもしっかりと感じることができるならたくさん摂ってもいいのではないかと思いたくなりますよね。
しかし、いくつか懸念点が指摘されています。
- 人工甘味料の甘さに慣れると甘みを感じにくくなってしまい、より甘みに対して強い欲求がでてしまう。
- 人工甘味料を習慣的に摂取したり、多く摂取すると食欲が刺激され、食事量が増える可能性がある。
- 人工甘味料がお腹の中の環境(腸内細菌叢といいます)を変えてしまう可能性がある。
人工甘味料は血糖を上げることなく、甘みを感じることができる優れたものですが、デメリットなどについていまだわかっていないことも多く、過剰な摂取は控えたほうがいいでしょう。
糖分は控えたほうがいいのはわかったけど塩分はどうすればいいですか?
塩分を多くとりすぎると高血圧の原因に。血圧が上がると、腎臓に負担がかかったり、動脈硬化が進んで脳梗塞・心筋梗塞のリスクが上昇すると言われています。
糖尿病の患者さんにおいて食塩の摂取量は男性で1日7.5g未満、女性で6.5g未満が目標値です。高血圧のある方は男女とも1日6.0g未満の摂取量が目標となります。
外食や会食はしてもいいですか?
糖尿病の患者さんでも食事療法を行っているからといって、外食や会食をしてはいけないということはありません。しかし、外での食事はおいしい食事や知人と楽しく過ごしたりして、ついつい食べ過ぎたりしてしまうことも少なくありません。
以下に外食のポイントについてまとめました。
- 1度に食べる量は普段と変わらないことを理解。
- 1回の食事量や食事内容について把握。
- サラダやおかずなどを組み合わせて単品料理は極力避け、定食類などを選ぶ。
- 取り分けができる、残しやすい料理を選ぶ。
- 食べる前に大まかな主食(できれば副食も)を調整(小盛りにしてもらうなど)。
- 食べ放題のお店ではどのような料理があるか確認し、量を決める。
- 野菜類を積極的に摂取。
- 揚げ物などカロリーが高いものを摂り過ぎないように。
- デザートは別腹ではないことを意識。
カーボカウントとは何ですか?
 院長 藤田
院長 藤田カーボカウントとは、炭水化物の中の糖質の量を計算して、食事に含まれる糖質量を把握して食後の血糖値をコントロールするやり方です。
炭水化物(Carbohydrate:カーボハイドレート)を数える(Count:カウント)の英語名から名付けられました。
日本では当初、インスリン治療が必要な1型糖尿病の患者さんを対象に使用されていましたが、最近は、2型糖尿病の患者さんにも活用されるように。
カーボカウントのやり方は2種類あります。
1日の摂取炭水化物量を決めて、それぞれの食事ごとの炭水化物量を均等にすることで血糖値の上昇を一定にし、血糖コントロールを行う「基礎カーボカウント」と、摂取する炭水化物の量に合わせてインスリン量を調整する「応用カーボカウント」です。
基礎カーボカウントは、すべての糖尿病の患者さんに使用でき、応用カーボカウントはインスリン治療が必要な1型糖尿病患者さんを主な対象としています。
ここでは基礎カーボカウントについて簡単に説明していきます。
食後の血糖に影響を与えるのはカロリーでなく、炭水化物(糖質)
炭水化物のうち主食に含まれる多糖類やお菓子、ジュース、果物に含まれる単糖類や二糖類が最も食後の血糖に影響を与えます。
糖質を多く含む食品とそうでない食品
| <糖質の多く含む食品> | <糖質の少ない食品> |
| ご飯、パン、めんなどの穀物 いも類(さつまいも、じゃがいも) 炭水化物の多い野菜、種実 (根菜、かぼちゃ、とうもろこしなど) 豆類 | 魚介類 大豆 卵、チーズ 牛肉、豚肉、鶏肉やその加工品(ハムなど) |
| 果物 | 油脂類(サラダ油、バター、マーガリン) |
| 牛乳、乳製品(チーズは除く) | 野菜(葉物類)、海藻、こんにゃく |
| 調味料 (みそ、ケチャップ、みりん、ソース、カレールウ) | マヨネーズ、塩、こしょう |
| ジュース、菓子類 |
1回の食事で摂取する炭水化物量を決める
今回は例として、栄養指導で「1日の総エネルギー摂取量を2000カロリー、炭水化物を50%にしましょう」といわれた方で考えてみます。
*総エネルギー摂取量や炭水化物の割合は人により異なります。
①1日に摂取する炭水化物量でのカロリーを決める
炭水化物は50%なので、
1日に摂取する炭水化物量(カロリー)=2000(カロリー)×0.5 (50%)=1000カロリー
②1日に摂取する炭水化物量(g)を決める
炭水化物は1gで4カロリーなので、
1日に摂取する炭水化物量(g)=1000÷ 4 =250g
③1回に摂取する炭水化物量(g)を決める
1日3食なので、
250÷3=83.333・・・・・
よって、1食約80gの炭水化物をとることが目安となります。
カーボカウントのコツは主食に含まれている炭水化物を把握することです。よく食べられている主食の糖質量を載せますので、普段ご自身がどれくらいの糖質量を摂取しているか考えてみるのもいいでしょう。
アルコールは飲んでもいいですか?
1日の摂取アルコール量の上限は25gほど。
アルコールは適量を飲むと、ストレスを解消する効果があったり、円滑なコミュニケーションにもつながることが期待できます。
しかし、過剰に摂取すると、肥満や肝機能障害、アルコール依存など体と心の健康を損なう原因に。
糖尿病の患者さんのアルコール摂取において、気をつけていただきたいことがいくつかあるので説明していきます。
まずは、食事摂取量の増加です。
アルコールを摂っていると知らず知らずのうちに食べる量が増えてしまうことがあります。指示されたエネルギー量を超えないように注意が必要。
薬物療法を行っている方は、相互作用にも注意が必要です。とくにインスリンや、SU薬などの経口血糖降下剤で薬物治療をしている方は、アルコールの急性効果として低血糖を起こしやすくなります。
食事をとらずに飲酒するのは避けたほうがいいでしょう。
ビグアナイド薬は副作用の乳酸アシドーシスが起こりやすくなったり、SGLT2阻害薬では脱水が起こりやすくなるので、過度のアルコールを摂りすぎないよう注意しましょう。
糖質ゼロや糖質オフと記載されているお酒にも注意が必要。
消費者庁の食品表示基準では、100g当たり(清涼飲料水などは100ml当たり)0.5g未満の糖質を含む食品は糖質ゼロと表示可能です。
つまり、微量ですが、糖質が含まれています。おつまみを食べていないからたくさんアルコールを飲んでも平気だと言って多量のアルコールを摂取したら、糖質も多くとっていたということにもなりますので気をつけましょう。
では、どれくらいアルコールを摂取してもいいのかといいますと、1日の摂取アルコール量の上限は25gほどです。
目安としてアルコール量が20gのお酒の量を以下に載せておきますので参考にしていただき、お酒と楽しく付き合っていただければと思います。
まとめ
今回は、糖尿病の治療の一つである食事療法についてお話いたしました。
食事療法はすべての糖尿病患者さんが行うべき治療方法です。適正なエネルギー量でバランスのとれた食事を規則正しく食べることで、血糖の改善、体重減少など数多くのメリットが。
一方で、食事療法は一部複雑な内容も含まれていることから、誤解や間違った情報がインターネットなどで散見され、患者さんが翻弄されてしまうこともしばしば見受けられますので、注意が必要です。
食事療法に限りませんが、治療は継続が大事です。
正しい知識を身につけていただくことで、極端な食事制限をせず、外食も上手に活用するなどストレスの少ない食生活を送っていただきたいと思います。
食事は人生の楽しみの一つです。今回のお話でみなさんが食の楽しみを失うことなく食事療法を続けていくきっかけとなれば幸いです。
参考文献
- 糖尿病診療ガイドライン2019 南江堂. 2019年.
- 糖尿病治療ガイド2020-2021 文光堂. 2020年.
- Ueki K, et al. Effect of an intensified multi factorial intervention on cardiovascular outcomes and mortality in type 2 diabetes (J-DOIT3): an open-label, randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017 Dec;5(12):951-964. doi: 10.1016/S2213-8587(17)30327-3.
- Look AHEAD Research Group. Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2013 Jul 11;369(2):145-54. doi: 10.1056/NEJMoa1212914. Epub 2013 Jun 24. Erratum in: N Engl J Med. 2014 May 8;370(19):1866.
- Chen L, Pei JH, Kuang J et al. Effect of lifestyle intervention in patients with type 2 diabetes: a meta-analysis. Metabolism. 2015 Feb;64(2):338-47. doi: 10.1016/j.metabol.2014.10.018. Epub 2014 Oct 23.
- Gillespie SJ, Kulkarni KD, Daly AE. Using carbohydrate counting in diabetes clinical practice. J Am Diet Assoc. 1998 Aug;98(8):897-905. doi: 10.1016/S0002-8223(98)00206-5.
- Huang XL, Pan JH, Chen D et al. Efficacy of lifestyle interventions in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Eur J Intern Med. 2016 Jan;27:37-47. doi: 10.1016/j.ejim.2015.11.016.
- Zhang X, Devlin HM, Smith B et al. Effect of lifestyle interventions on cardiovascular risk factors among adults without impaired glucose tolerance or diabetes: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2017 May 11;12(5):e0176436. doi: 10.1371/journal.pone.0176436.
- Imai S, Fukui M, Kajiyama S. Effect of eating vegetables before carbohydrates on glucose excursions in patients with type 2 diabetes. J Clin Biochem Nutr. 2014
- 日本老年医学会 HPHP